高齢化が進む中、「最期は住み慣れた自宅で迎えたい」と望む人が増えています。しかし、現実には病院や施設での看取りが多く、在宅での看取りにはさまざまな課題が伴います。特にケアマネジャーは、本人・家族・医療・介護の間に立ち、看取りの支援を調整する重要な役割を担っています。
この記事では、在宅看取りの現状と問題点、ケアマネジャーができる支援の工夫について詳しく解説します。
在宅看取りの現状|希望と現実のギャップ

厚生労働省の調査によると、「自宅で最期を迎えたい」と希望する人は約6割にのぼります。しかし、実際に自宅で看取られる人は全体の約15%程度にとどまっています。
希望が叶わない理由:
- 医療体制が整っていない
- 家族の介護負担が大きい
- 急変時の対応が不安
- 看取りに関する情報不足
特に独居や高齢夫婦世帯では、在宅看取りのハードルが高く、病院への搬送が選ばれるケースが多くなります。
在宅看取りにおけるケアマネジャーの役割

ケアマネジャーは、在宅看取りを支える“調整役”として、以下のような業務を担います。
1. 本人・家族の意思確認と共有
- 「どこで最期を迎えたいか」「延命治療は望むか」などの意思を確認
- 家族との温度差を調整し、共通認識をつくる
- 医療職との情報共有を図る
2. 医療・介護サービスの連携
- 訪問看護・訪問診療の導入
- 夜間対応可能な事業所の選定
- 緊急時の連絡体制の構築
3. ケアプランの再構築
- 看取り期に合わせたサービス内容の見直し
- 介護負担軽減のためのショートステイやヘルパーの活用
- 家族支援も含めた包括的なプラン設計
「ケアマネがいなければ、在宅看取りは成り立たなかった」と語る家族も少なくありません。
在宅看取りの課題とケアマネの悩み

現場では、ケアマネジャー自身も多くの葛藤を抱えています。
1. 医療との連携が難しい
- 訪問診療医が少ない地域では、医療連携が困難
- 急変時の対応を医療側に任せきれない不安
- 看護師との情報共有が不十分なケースも
2. 家族の不安が強い
- 「本当に自宅で看取れるのか」という不安
- 介護疲れや精神的負担が限界に達することも
- 死に対する価値観の違いが衝突を生む
3. ケアマネ自身の経験不足
- 法的・制度的な知識不足
- 看取り支援の経験が少ないケアマネも多く、対応に迷う
- 死を扱うことへの心理的ハードル
在宅看取りの支援にあたるケアマネジャーは、制度と現場の“隙間”に立たされることが少なくありません。医療職のように診断や処置ができるわけでもなく、介護職のように直接的なケアを担うわけでもない。けれど、本人の意思を汲み、家族の不安に寄り添い、24時間体制の支援を組み立てるのはケアマネの役割です。 「この人の最期を、どう支えればいいのか」——その問いに、正解はありません。制度の限界と家族の感情の間で揺れながら、それでも“誰かの最期に関われること”に誇りを持っているケアマネが、現場には確かに存在しています。
ケアマネができる支援の工夫
在宅看取りを支えるために、ケアマネジャーができる工夫は多岐にわたります。
1. 看取り期のアセスメントを丁寧に
- 本人の意思だけでなく、家族の覚悟や支援体制も確認
- 医療職との連携を前提に、ケアプランを柔軟に設計
- 「何が起きるか」「どう対応するか」を事前に共有
2. 多職種連携を“見える化”する
- 緊急時の連絡先一覧を作成
- 訪問看護・医師・ヘルパーの役割分担を明確に
- 家族にも「誰に何を頼めるか」を伝える
3. 家族の心のケアも意識する
- 不安や葛藤を言葉にできる場をつくる
- グリーフケアの視点を持ち、死後の支援も視野に入れる
- 「一人じゃない」と感じられる関係性を築く
看取り期には、予定通りに進まないことの方が多く、介護者の言葉にならない不安や、本人の微細な変化に寄り添う柔軟さが求められます。 「制度ではこうだけど、今はこの人にとって何が一番安心か」——その問いを日々繰り返しながら、ケアマネは“正しさ”より“納得感”を優先する支援を組み立ててかなければならいこともあります。支援の工夫とは、サービスの組み合わせだけでなく、“人としての関わり方”を設計することでもあるのです。
現場の声:在宅看取りを支えたケアマネの実感
「最初は“無理だと思う”と言っていた家族が、最期に“自宅でよかった”と涙を流してくれた。その瞬間、ケアマネとしての役割の重みを実感した。」
「医師との連携がうまくいかず、夜間の急変に対応できなかった悔しさは今でも残る。だからこそ、事前の準備と連携が何より大切だと思う。」
まとめ|在宅看取りは“ケアマネの支援力”で叶う
ケアマネジャーは、現場での支援に悩みながらも、本人や家族の希望を叶えたいと願っているはずです。看取りは、制度やサービスだけではなく、“人の支え”によって成り立つケアです。
ケアマネジャーが、医療・介護・家族をつなぎ、最期まで安心して過ごせる環境を整えること。それが、在宅看取りを可能にする鍵となります。
まずは、本人の思いに耳を傾け、家族の不安に寄り添い、チームで支える体制を築いていきましょう。
ケアマネにおすすめ
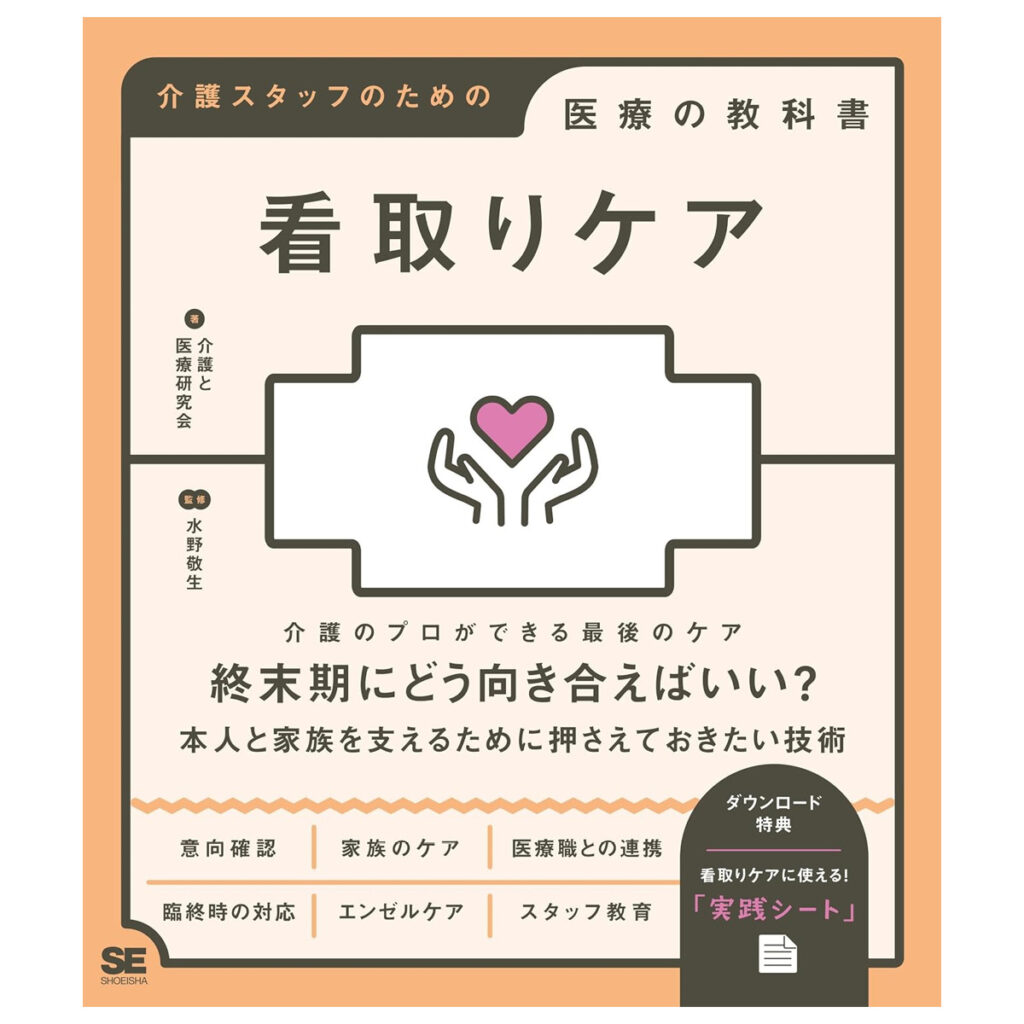
看取りケア 介護スタッフのための医療の教科書
終末期にどう向き合えばいい?
本書では事前の意向確認、臨終時の対応、医療職との連携など、看取りに関する知識と技術が実際の流れに沿って解説されています。
遺族への接し方や、近年増加している在宅での看取りにも対応。介護職として入所者の終末期にどう向き合うか、知っておきたい情報が詰まった一冊です。
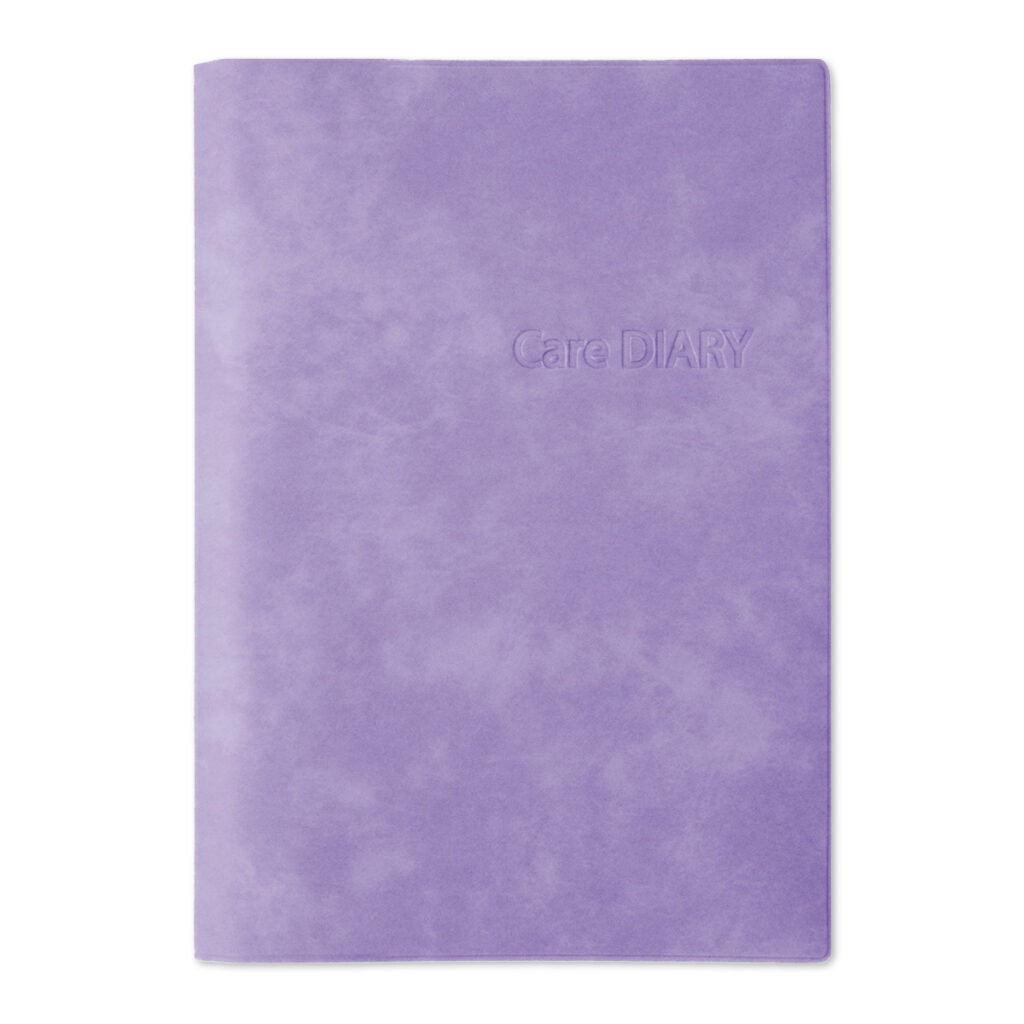
最近はスケジュールをアプリで管理するという人も多いと思いますが、なんでもすぐに自由に書き込める手帳はやっぱり便利です。
キャプスのケアマネ向け手帳はカラーラインナップ豊富。最新版介護サービスコード表がついているタイプと、サービスコード表なしの「Light」が人気です。
早期割でのご注文は9月末までですのでお早めに♪
こちらの記事もおすすめ
投稿者プロフィール

- 看護師・保健師としての経験後、現在は高齢者のケアマネジメント業務に奮闘中。ベビーから高齢者の方まで幅広く関わっています。
最新の投稿
 訪問看護2025年8月27日パーキンソン病の訪問看護は医療保険?介護保険?助成制度についても解説
訪問看護2025年8月27日パーキンソン病の訪問看護は医療保険?介護保険?助成制度についても解説 訪問介護2024年6月27日介護職員の資格一覧!ホームヘルパー1級・2級との違いも解説
訪問介護2024年6月27日介護職員の資格一覧!ホームヘルパー1級・2級との違いも解説 訪問介護2024年4月11日軟膏塗布や在宅酸素などに関わる行為はヘルパーが実施可能?実施可能な範囲について解説!
訪問介護2024年4月11日軟膏塗布や在宅酸素などに関わる行為はヘルパーが実施可能?実施可能な範囲について解説! 訪問看護2024年1月24日看護師の病院以外の就職・転職先|看護師が活躍できる職場をご紹介
訪問看護2024年1月24日看護師の病院以外の就職・転職先|看護師が活躍できる職場をご紹介


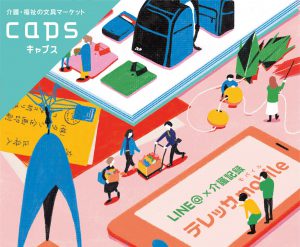
.jpg)
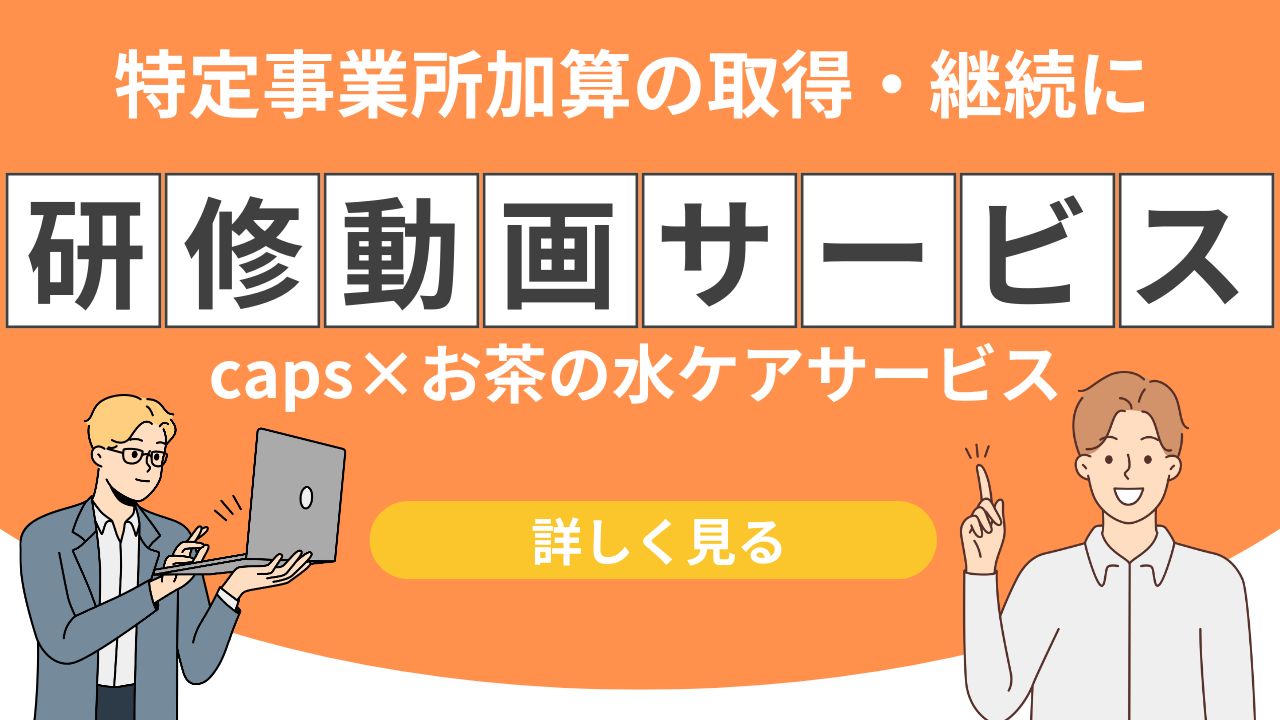

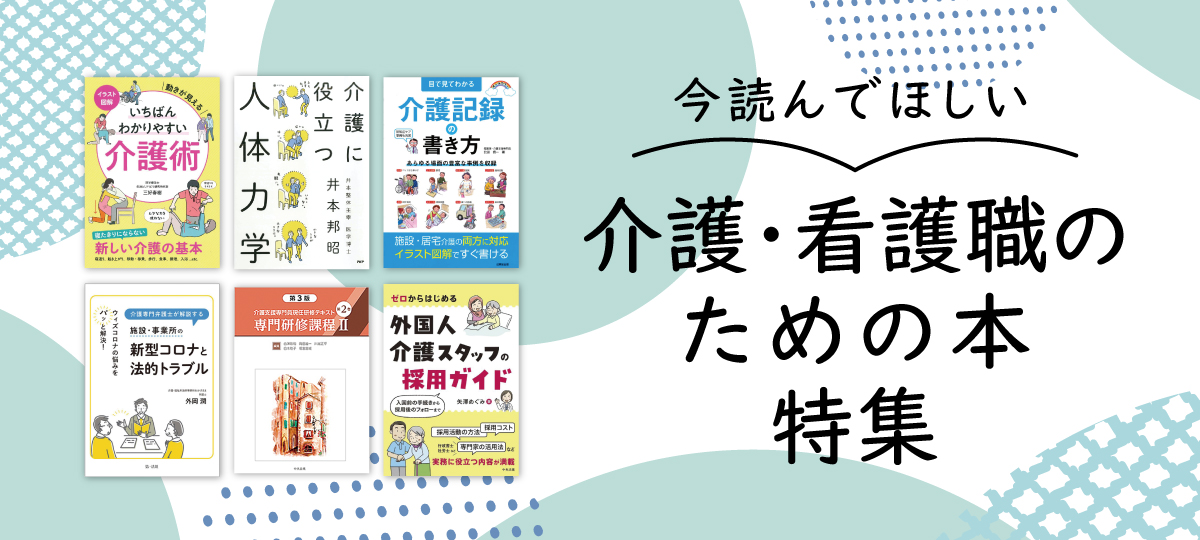
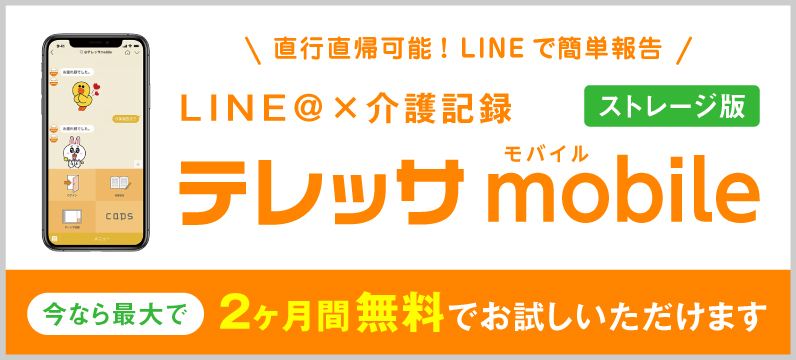

コメント