発達障害のある子どもは、時間の感覚や予定の見通しをつかむことが苦手な傾向があります。「朝の支度に時間がかかる」「予定変更にパニックになる」「何度言っても行動できない」——そんな悩みを抱える保護者は少なくありません。
時間割を見て持ち物の準備をするのが苦手だったり、そもそも先生に言われたことをメモするのを忘れていたり。
さらには時間通りに行動するのが苦手で、遅刻してしまうことも。
そんなとき、「○○しなさい」「どうして○○できないの」「明日の準備は済んだ?」と口頭で注意をしてしまっていませんか?
忘れ物や遅刻が多い子供は注意される機会も増え、子供の自己肯定感が下がってしまいます。
この記事では、生活ボードや視覚支援を活用したスケジュール管理の工夫、家庭や支援現場でできる実践例、そして子どもの“できる”を引き出すためのヒントを紹介します。
発達障害のある子どもがスケジュール管理を苦手とする理由
発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などが含まれます。それぞれ特性は異なりますが、共通して以下のような困難を抱えやすいです。
よくある特性:
- 時間の流れを把握しづらい
- 予定の変更に強い不安を感じる
- 抽象的な指示が理解しにくい
- 自分で行動を切り替えるのが苦手
- 言葉だけの説明ではイメージが湧かない
こうした特性に対して、「何度言ってもできない」と叱るのではなく、子どもが“理解しやすい形”で情報を伝える工夫が必要です。
スケジュール管理の基本は“見える化”と“予測可能性”
発達障害のある子どもにとって、スケジュール管理の鍵は「見える化」と「予測可能性」です。予定や手順を視覚的に示すことで、安心感と自発的な行動につながります。
見える化のメリット:
- 予定が目に見えることで不安が減る
- 自分で確認できるため、指示待ちが減る
- 行動の切り替えがスムーズになる
- 予定変更にも柔軟に対応しやすくなる
「次に何をするか」がわかるだけで、子どもの行動は大きく変わります。
生活ボードを使ったスケジュール管理

ホワイトボードのマグネットシールを確認することで、一日の予定、一週間の予定が視覚で分かります。
発達障がいには、視覚で見えないものを理解しにくかったり、見通しが立たないことに対して不安が強くなるといった特性のある子もいます。生活ボードを使用することで、視覚的に・見通しを立てて行動することができるようになります。

1日の流れは朝・昼・夜に分け、それぞれの時間帯で「やるべきこと」をイラストつきのマグネットシールで理解できます。
「まだ」⇒「できた」に自ら移動する楽しさと、達成感を味わうことができ、自分で準備ができるようになるのです。
「できた」ことが増えることで自信になります!
「日付・じゅんびするもの」の部分は一般的なホワイトボードと同じように文字を書くことができ、繰り返し使うことができます。マグネットは全部で80枚。予備シートもあるのでオリジナルの予定を作ることも可能です。
視覚支援のバリエーションと工夫

生活ボード以外にも、視覚支援にはさまざまな方法があります。子どもの年齢や特性に合わせて使い分けましょう。
視覚支援の例:
- タイムタイマー:残り時間が視覚的にわかる時計
- スケジュールカード:予定を1枚ずつ提示する方法
- チェックリスト:やることを順番に確認できる
- カレンダー:週単位・月単位の予定を把握する
- 色分け:活動ごとに色を変えて視認性を高める
「朝は青」「学校は緑」「帰宅後は黄色」など、色で予定を分類すると、理解しやすくなります。

ソニック トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
家庭でできるスケジュール管理の工夫
家庭では、日常の流れを整えることがスケジュール管理の第一歩です。以下のような工夫が効果的です。
1. 毎日のルーティンを固定する
- 起床・食事・入浴・就寝などの時間を一定に
- 休日も大きく崩さないことで安心感を保つ
- 「○時になったら○○する」と予告する習慣をつける
2. 予定変更は“予告”と“理由”をセットで
- 「今日は病院に行くから、帰宅後の遊びはなし」など
- 変更前にカードを差し替えて説明する
- 「○○が終わったら△△できるよ」と見通しを示す
3. “できた”を積み重ねる仕組みをつくる
- スタンプやシールで達成感を可視化
- 「全部できたら好きな絵本を読もう」などのご褒美設定
- 失敗しても責めず、「次はどうする?」と一緒に考える
よくある悩みとアドバイス

Q. 生活ボードを嫌がる場合はどうすれば?
→ 子どもが好きなキャラクターや色を使って、楽しい印象に変えると受け入れやすくなります。最初は短時間の予定から始めるのも効果的です。
Q. 予定変更でパニックになるのが心配…
→ 変更の“予告”と“代替案”をセットで伝えることで、安心感が生まれます。「今日は○○できないけど、代わりに△△しようね」と伝える習慣をつけましょう。
Q. 年齢が上がってきたらどう対応すれば?
→ 小学生以降は、カレンダーやスマホアプリなど、より抽象度の高いツールに移行していくのが理想です。本人の理解力に合わせて段階的に切り替えましょう。
まとめ:発達障害の子どものスケジュール管理は“見える安心”から始まる

時間の感覚や予定の見通しが苦手な子どもにとって、視覚的な支援は“安心して動ける”ための大切な手段です。
生活ボードやタイムタイマーなどのツールを活用しながら、子どもが「自分でできた」と感じられる経験を積み重ねていくこと。それが、将来の自立にもつながります。
まずは、今日の予定を“見える形”にしてみることから始めてみませんか。

こちらの記事もおすすめ
投稿者プロフィール

- 看護師・保健師としての経験後、現在は高齢者のケアマネジメント業務に奮闘中。ベビーから高齢者の方まで幅広く関わっています。
最新の投稿
 訪問看護2025年8月27日パーキンソン病の訪問看護は医療保険?介護保険?助成制度についても解説
訪問看護2025年8月27日パーキンソン病の訪問看護は医療保険?介護保険?助成制度についても解説 訪問介護2024年6月27日介護職員の資格一覧!ホームヘルパー1級・2級との違いも解説
訪問介護2024年6月27日介護職員の資格一覧!ホームヘルパー1級・2級との違いも解説 訪問介護2024年4月11日軟膏塗布や在宅酸素などに関わる行為はヘルパーが実施可能?実施可能な範囲について解説!
訪問介護2024年4月11日軟膏塗布や在宅酸素などに関わる行為はヘルパーが実施可能?実施可能な範囲について解説! 訪問看護2024年1月24日看護師の病院以外の就職・転職先|看護師が活躍できる職場をご紹介
訪問看護2024年1月24日看護師の病院以外の就職・転職先|看護師が活躍できる職場をご紹介


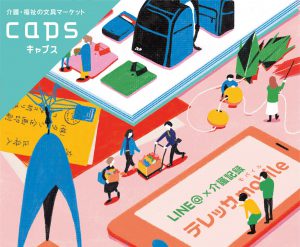
.jpg)
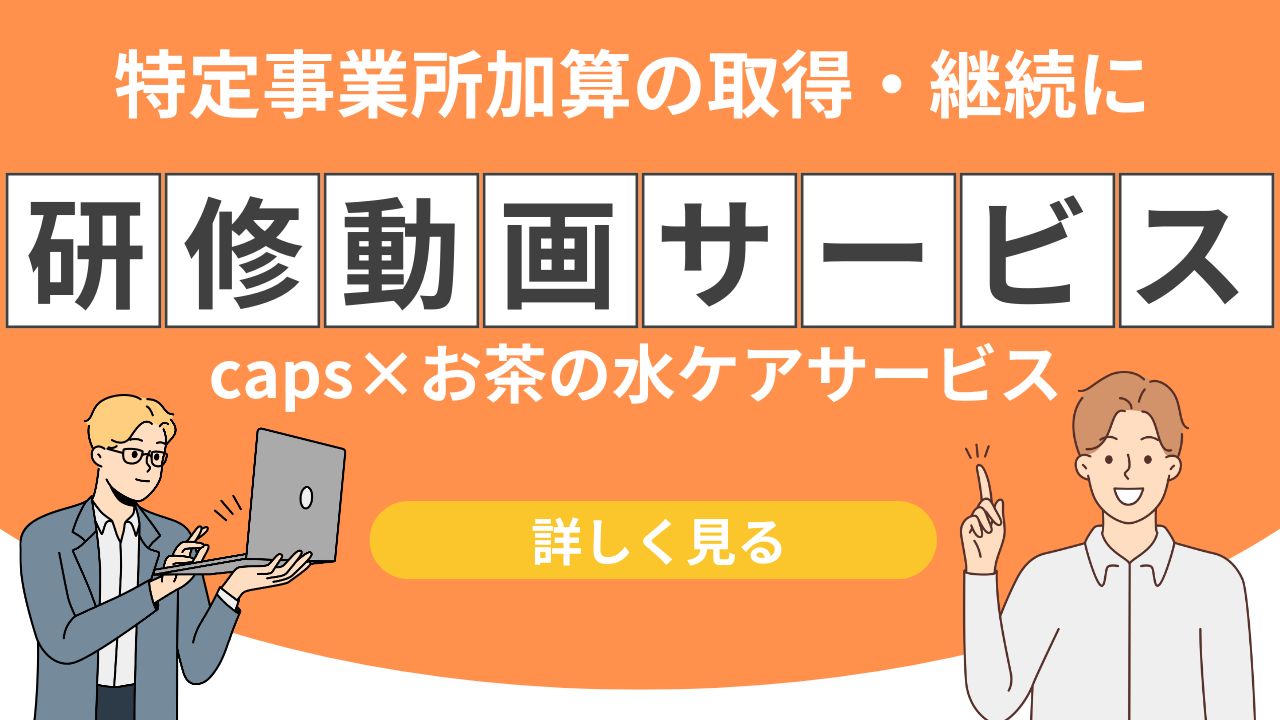

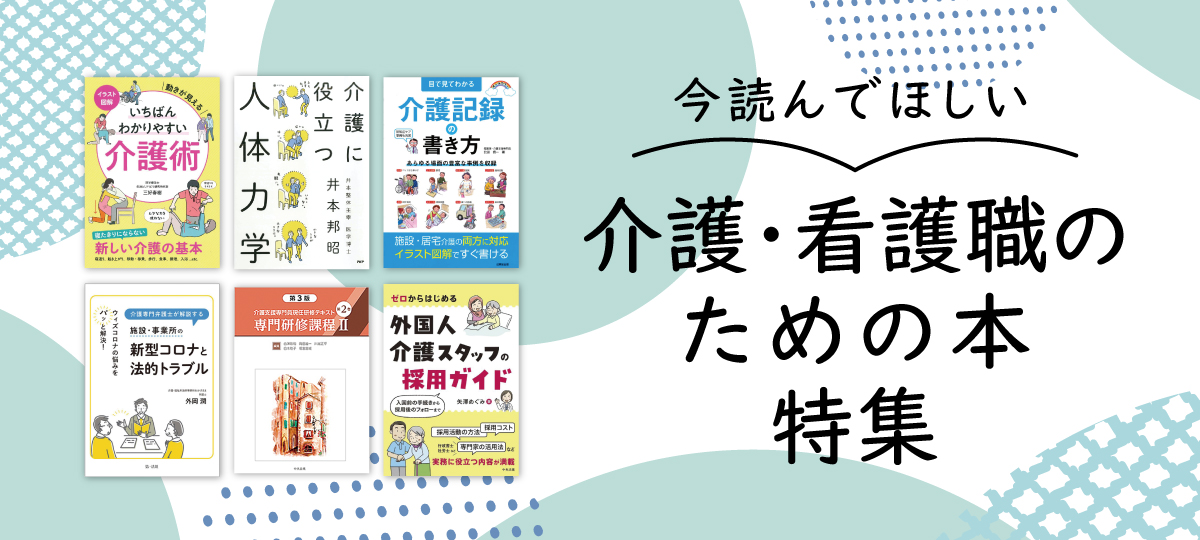
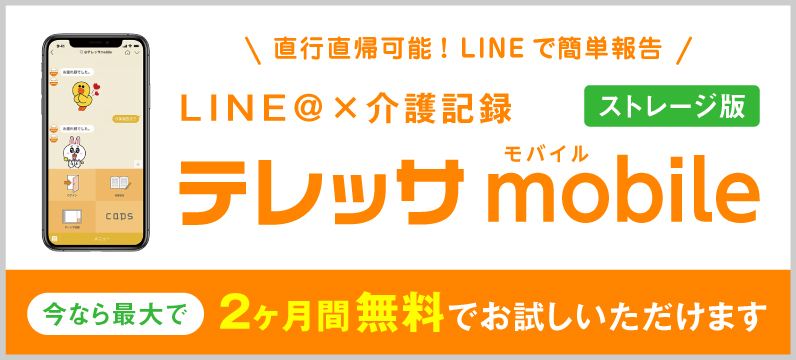

コメント