この記事では、ホームヘルパー2級取得を考えている方に、そのメリットと講座の体験談をメインでお伝えしています。
今や超高齢化社会、それでも介護人材が少なく、人材不足を嘆いている事業所が本当にたくさんあります。いわば、介護資格保持者は重宝される時代です。さらに介護技術は、自身の周りで介護が必要になった場合にも役立ちます。
介護分野は考えたことがなかったという人も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
ホームヘルパー2級とは

介護の仕事をするうえで一番よく聞く資格「ホームヘルパー2級」は、正式名称を「訪問介護員養成研修2級課程」といいます。介護職の入門資格ともいえる資格で、高齢者宅でサービス提供を行う訪問介護だけでなく、通所介護事業所(デイサービス)や施設で働く方にもおススメの資格です。
まずはホームヘルパー2級の基本的な概要を確認しましょう。
現在は「介護職員初任者研修」に
「ホームヘルパー2級」は、現在は「介護職員初任者研修」という名称の資格に変わっています。
ヘルパー2級が介護職員初任者研修に変わったことで、学習内容にもいくつかの違いがあります。
- 介護職員初任者研修では「認知症の理解」に関する学習科目が追加
- 施設実習が必修ではなくなった
- 筆記試験が必須になった(ただし難易度は高くない)
このように、多少の違いがありますが、基本的な内容や資格の立ち位置は同じと考えて良いでしょう。
ヘルパー2級は介護職の登竜門!
ヘルパー2級(介護職員初任者研修)は、特別な受験資格はなく、難易度も高くありません。
そのため、介護の仕事をする方にとっては「登竜門」的な資格ですが、介護の仕事をすぐにしようとは考えていない、副業でできることを探している、将来役に立つ資格が欲しいという方にもぴったりの資格です。
何か資格を取りたいけど何がいいかわからない
無資格で介護の世界に入ったけど、何か資格を取得したい!
介護の仕事を始める前に、基本的な知識やノウハウを知っておきたい!
こういった方はぜひチャレンジしてみてくださいね。
体験談|ホームヘルパー2級取得を目指した理由

ここからは、実際にホームヘルパー2級資格を取得した私の体験談をご紹介します。
私は文系大学を卒業し、介護の会社に入社しました。
そのため、介護に関しては全くのド素人からのスタートです。資格がなくともヘルパーの仕事はできるのですが、できることに制限があったり、給与面で差が出てしまうことも。そこで私はホームヘルパー2級を取得しようと考えたのです。
①プライベートでも役立つ専門知識・技術が欲しかった
ホームヘルパー2級の資格を取得しようと思った理由は、やはり介護に関する専門知識や技術の習得がしたかったからです。
未経験で飛び込んだ介護業界、最初は聞きなれない言葉が多く、とても苦労しましたし、多くは大人を相手にする仕事なので、相手にも自分自身にもできるだけ負担の少ない介護技術を身に付ける必要があると感じました。介護の仕事を続けていくのなら、専門知識をつけ、自信をもって仕事をしていきたいと思ったのです。
私は介護の職に就いたのでもちろんですが、もしもこの仕事を辞めたとしても、プライベートでも介護の知識や技術は多くの場所で長く役に立つだろうと考えました。
②給与をUPさせたかった
資格取得によって給与を上げたい、という考えもありました。
介護職員の求人を調べると、保有資格に応じた資格手当を支給する施設が多くあるとわかります。
一般的に、ホームヘルパー2級の資格手当相場は2,000円~5,000円程度と言われているようです。
私が当時所属していた会社は、ホームヘルパー2級所有者に月3,000円程度の資格手当が支給されていました。
一度取得すれば更新もない資格なので、今後転職する場合にも条件面で有利になるだろうと考えました。
同じ介護の仕事をするのなら少しでも給与が高いほうがいいですよね。
③働きながら取得できる
仕事を続けながら取得できるというのも大きなポイントでした。
普段の仕事に支障が出るようなら、すぐに資格を取ろうとは思っていなかったと思います。
ホームヘルパー2級取得までの道のり

実際にホームヘルパー2級の資格を取得するまでの道のりをご紹介します。
介護職員初任者研修とは違う面もありますし、資格取得する機関によっても詳細は異なると思います。
働きながらヘルパー2級資格を取得した経験者の実例として、ご参照ください。
【1か月目】自宅学習
私の場合、所属していた企業がヘルパー2級講座を提供しており、自宅学習と通学の併用でした。様々な機関で介護職員初任者研修講座を開催していますが、だいたい同じような講座内容です。
最初の1か月はテキストを用いての自宅学習のみ。
各人が自分のタイミングで、決められた範囲のテキストを読み込んでいくスタイルでしたが、このテキストを読み込むだけでもたくさんの知識を得ることができました。
【2~3か月目】土日休みに通学
2か月目から、通学での学習がはじまります。
私が受講した会社では、毎週土・日に数時間ずつ、約2か月間の通学が必要でした。
テキストを用いての学習から、介護技術のレクチャーなどもあります。
介護技術の学習で特に思い出に残っているのは、紙おむつの着脱介助体験です。介護の仕事といえば排せつ介助はどうしても必要なものです。
2名1組になり、一方が介護者、もう一方が要介護者になります。
要介護者役はベッドに横たわり、介護者に紙おむつをつけてもらう、というなんとも気恥ずかしい体験でしたが、要介護者の立場も経験するということが、その後実際に介助を行う際にとても役に立ちました。
【4か月目】実際の介護現場で実習
学びの集大成として、施設実習がありました。
私が通った講座の場合、以下3か所での施設体験が必須でした。
- 通所介護事業所(デイサービス)
- 特別養護老人ホーム
- 訪問介護
訪問介護では、ベテランヘルパーさんに同行して1日に複数の利用者様宅を訪問、利用者様の食事の調理や入浴介助を行うなどしました。見聞きするだけでなく、実際に介助するというのは大変な面もあります。
実際の現場を講座の中で体験できるので、自身の職場選びにも参考になると感じました。
ホームヘルパー2級を取得して良かったこと

貴重な経験がたくさんできたホームヘルパー2級講座。プライベートにも役立つ知識も多く、資格を取得して良かったと思っています。
その中でも特にメリットを感じていることを3つご紹介します。
①介護の仕事についての理解が深まった!
まず、介護の仕事に対する理解が深まりました。
専門知識を得ることで、不安なく利用者様に接することができ、自信がつきました。
介護度や疾患などによって対応に注意が必要なこともありますが、講座で得た知識は現場できちんと役立ちますし、同じ介護職者のなかでも資格を持っていない人もいるので、差をつけられるということも良かったです。
②介護業界で働く上での選択肢が広まった!
資格を得ることで、介護業界で働く選択肢が広まりました。
実習内で訪問介護だけでなく、施設での仕事も体験でき、自分に合っているのはどちらか、ということを考えるきっかけもできました。
③仕事がたくさんある
介護業界は冒頭でもお伝えしたように常に人材不足の状態です。介護の資格を取得したことで、働くことのできる場がさらに増えたと感じます。
介護施設などは、スタッフの急な休みなどで人手が不足してしまい、入浴介助などの短時間の仕事が「単発バイト」として募集されているものも本当に多くあります。
資格を取得していればすぐに働くことができ、もう少し収入を増やしたいなというときも、隙間時間で稼げるものも多くあるので、自分のスキルとして今後もしっかり活かしていけると感じています。もしも今の会社を辞めるとしても、資格があれば転職にも有利になります。そう思うと、少し気が楽になった感覚もありました。
ヘルパー2級の資格取得で介護の仕事を自分のものにしよう!

今回は、私がヘルパー2級資格を取得した経緯や受講の過程、取得によるメリットなどをご紹介しました。
今から何か資格取得をと検討されている方は、「介護職員初任者研修」にぜひ挑戦してください。
もしも介護を本業としなくても、介護を副業にして稼ぐということもできます。国としても在宅介護を推奨しており、今後ますます需要は高まります。あなたの力を求めている企業がきっとたくさんありますよ。
投稿者プロフィール

- 神奈川県在住。Webライター。新卒で福祉企業に入社。ショートステイ、デイサービスで勤務したのち、デイ管理者や新規施設の立ち上げを担当。介護福祉士。2児のわんぱく男子を育てるフリーランスワーママ。
最新の投稿
 訪問介護2024年10月18日ホームヘルパー2級取得のメリットと講座体験談|需要の多い介護の仕事で副業も!?
訪問介護2024年10月18日ホームヘルパー2級取得のメリットと講座体験談|需要の多い介護の仕事で副業も!? 訪問介護2024年8月24日サービス提供責任者と管理者の違い|どちらがなりやすい?どちらが上なの?
訪問介護2024年8月24日サービス提供責任者と管理者の違い|どちらがなりやすい?どちらが上なの? 通所介護2022年12月4日デイサービスの送迎トラブル対策|事故予防と発生時の対応マニュアル
通所介護2022年12月4日デイサービスの送迎トラブル対策|事故予防と発生時の対応マニュアル 通所介護2022年12月2日デイサービスの受け入れを拒否できる正当な理由|法律と事例から詳細解説
通所介護2022年12月2日デイサービスの受け入れを拒否できる正当な理由|法律と事例から詳細解説


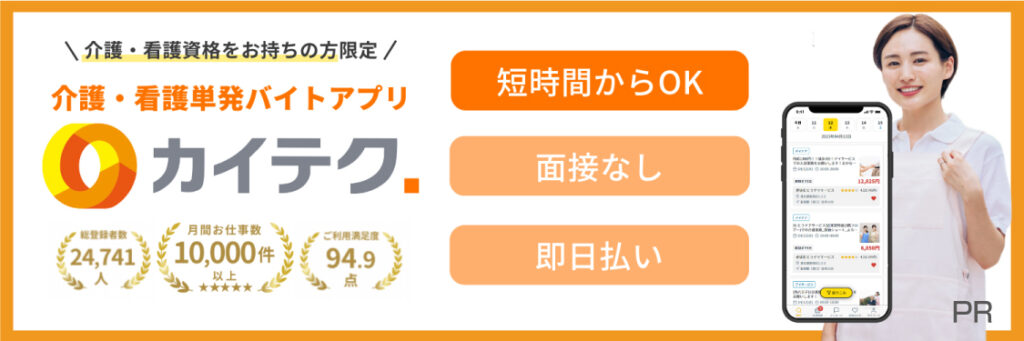
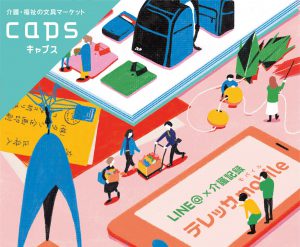
.jpg)
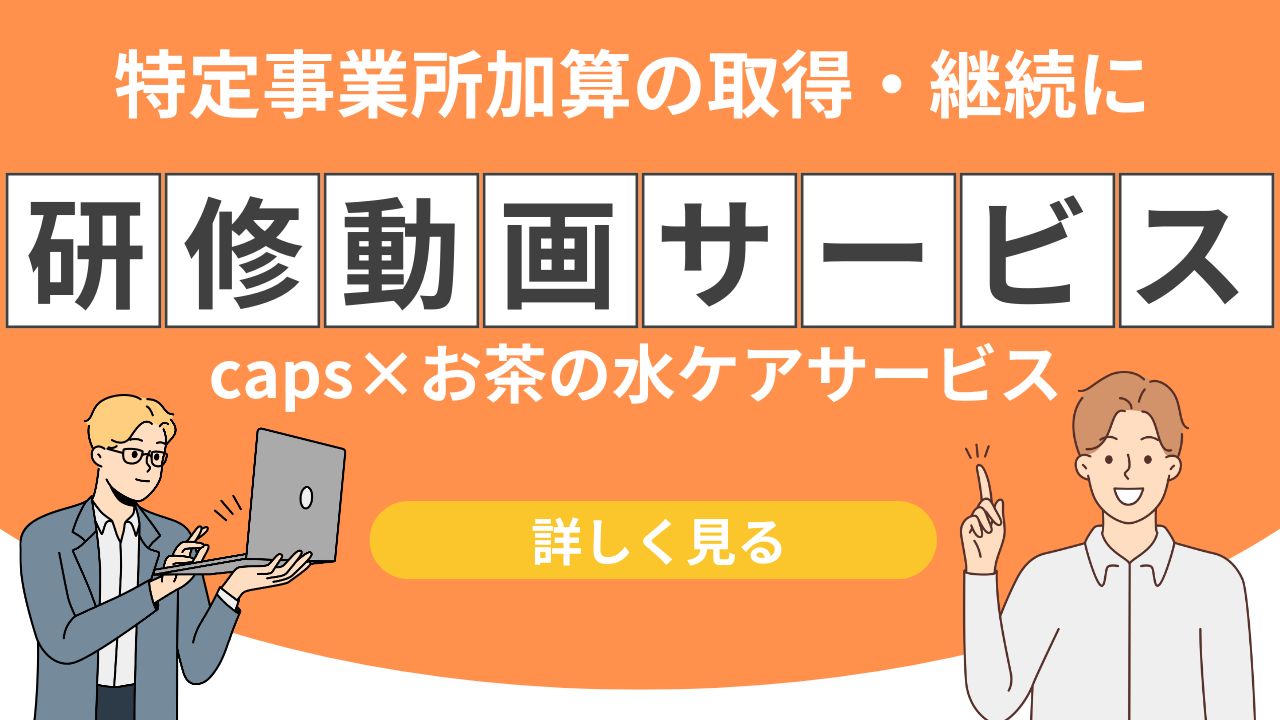

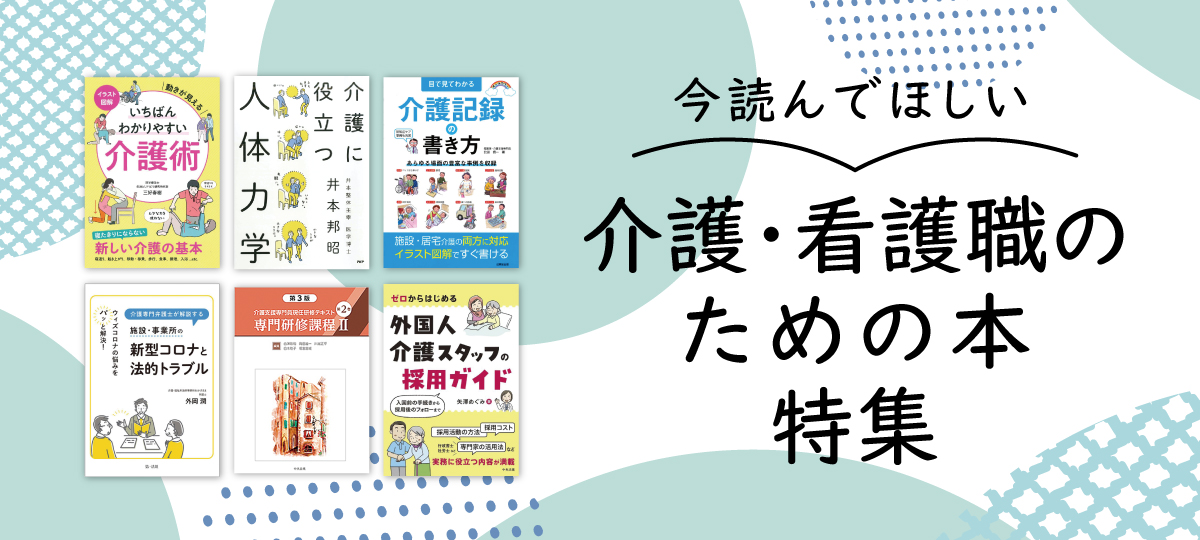
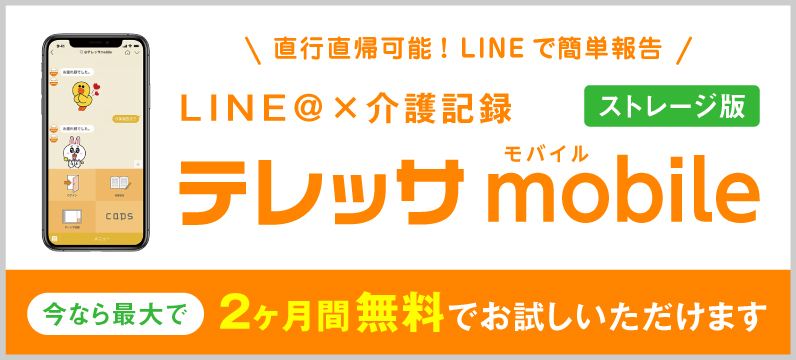

コメント