「とりあえず、ケアマネジャーに!」
と、業務範囲外の依頼が舞い込んでいませんか?
家族間や介護現場でよく耳にするこの言葉。多くのケアマネが、本来の職務を超えた依頼に悩まされています。通院の付き添いや入院準備、時には生活費の相談や買い物代行など、「え?これも私の仕事?」と思うような内容が舞い込むのが現実です。
ケアマネは、介護サービスを必要とする方に最適な支援を提供する“調整役”。ところが、その重要性が十分に理解されず、しばしば「何でも屋」扱いされてしまうことがあります。
この記事では、そうした業務外の依頼の背景や対処法、専門性の守り方について考えていきます。
ケアマネに押し寄せる「何でも屋」問題

身寄りがなく金銭的にも困窮している利用者の場合や、介護保険等の公的支援では対応が出来ない場合等、緊急にケアマネジャーが対応することも仕方がないことと、実際に私も感じた経験があります。
最近は特に高齢者が抱える課題が多様化・複雑化し、ケアマネジャーの業務量も役割もますます増加し、悩んでいるケアマネジャーも多いようです。実は、それが原因で退職や離職を考えたり、心を病んでしまっている人もいるほどです。ケアマネジャーにとって利用者や家族との関係は業務遂行する上で大変重要なファクターですから。
ケアマネの業務とは?
まず、基本に立ち返って「ケアマネジャーとは」「ケアマネジャーの業務とは」を思い出してみましょう。
介護保険法では、「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービス等を利用できるよう、その他サービス事業者との連絡調整を行う者であるとしています。
また、その業務内容は、居宅における要介護・要支援者に関連する業務と介護保険施設における要介護者に関する業務、包括支援センター等での相談支援計画作成業務とに分かれています。
ケアマネジャーの業務の本質はここにあるということを忘れないでください。
よくある業務範囲外の依頼とその実態

さて、厚生労働省の第5回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の資料では、介護サービスの利用者やその家族のうち、ケアマネジャーに対して本来の業務に含まれない支援も「依頼できる」と思っている人は約7割にのぼります。
特に、ケアマネジャーの業務に含まれない「定期的な見守り訪問」「公的機関への申請代行」「通院の付き添い・送迎」などが、依頼できる支援として広く認識されているようです。
一方で、ケアマネジャー以外に相談できる人が「いない」人は約半数。多くの利用者・家族が、ケアマネジャーを唯一の拠り所として頼らざるを得ない実態も改めて浮き彫りになっています。
第5回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 資料|厚生労働省
事例で見る何でも屋の実態
では、実際にあったケアマネジャーへの業務外の依頼を見てみましょう。こんな経験、ありませんか?
事例1 デイサービスの送迎の補助や送り出し
「 ヘルパーが間に合わない」「拒否があるので説得してほしい」など緊急に頼まれ、気づけば日課になっている。
事例2 利用者の入退院時の生活用品等の調達
入院時、パジャマや日用品の買い物・病棟への持参を依頼された/家に忘れてきた保険証を取ってきてほしいと言われた/退院後の生活用品や食品の準備を頼まれた。
事例3 介護保険制度上では対応できない生活支援
「銀行等の手続き」「通帳や財布の確認」「ゴミ出しや粗大ごみの対応」「買い物代行」など頼まれて仕方なくやってしまった。
事例4 長時間の電話対応
サービス調整等に関わらない電話や家族や利用者本人からの長電話が勤務時間外や休日にもかかってくる。
事例5 金融機関や介護保険以外の行政各種手続き・申請の代行
「この通帳でお金をおろしてきてくれ」「住民票をとってきてくれないか」など気軽に依頼された。
事例6 モニタリングや定期の安否確認を除く緊急訪問
居宅サービス事業者から事故や特変時の連絡のケアマネジャーの優先度が高い。特に認知症の人の徘徊等にはすぐ呼び出される。
私の事業所でも過去に「病院までの送迎を行いました」「片付けを頼まれたので片付けてきました」「銀行の付添いをしました」等の報告が来たことが度々ありました。
話を聞くと本当に替えの効かないどうしようもないケースやタイミングが年に数回あったりします。しかし、だからと言って漫然とその行為を続けることはできません。
ケアマネ自身が行うことのリスクや、個々の利用者に対してより効果的で合理的な別のやり方を検討しましょう。
やってはいけない業務範囲外の行為
必要に応じて仕方なく行わなければならない部分も当然出てくると思いますが、中にはケアマネジャーが行ってはいけない行為があります。以下に項目を挙げています。法令違反になりますので注意しましょう。
- 金融機関やその他各種機関の手続きや申請の代行・支援
- 入院・入所時の身元保証
- 生活費等、日常的な預貯金の引き出し・振込代行
- 死後事務
- 土地や住宅、相続に関する手続きや申請の代行・支援
- 財産管理
ケアマネジャーが便利屋になってしまう4つの理由

では、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。その背景にはいくつかの要因があります。
① 専門職としての役割の認知不足
利用者・家族・関係者の中には、ケアマネの仕事を「介護に関することは何でもやってくれる人」と誤認している人もいる。これは制度そのものが複雑であることや、説明不足も原因。
② 「断れない」心理と関係性の遠慮
ケアマネ自身が、「断ると利用者や家族との関係が悪くなるのでは」と心配して、つい引き受けてしまう。
③ 職場の体制・職域の曖昧さ
事業所によっては「ケアマネが現場も見るのが当たり前」といった空気が根強く、明確な線引きが難しい。
④ 「ついで」「善意」が広がる構造
例えば、「ついでだから送迎と付き添いも」「ついでだから家族の様子を見て来て」といった小さな頼まれごとが、やがて当たり前になっていく。
ケアマネの業務範囲の線引き:判断と説明のポイント
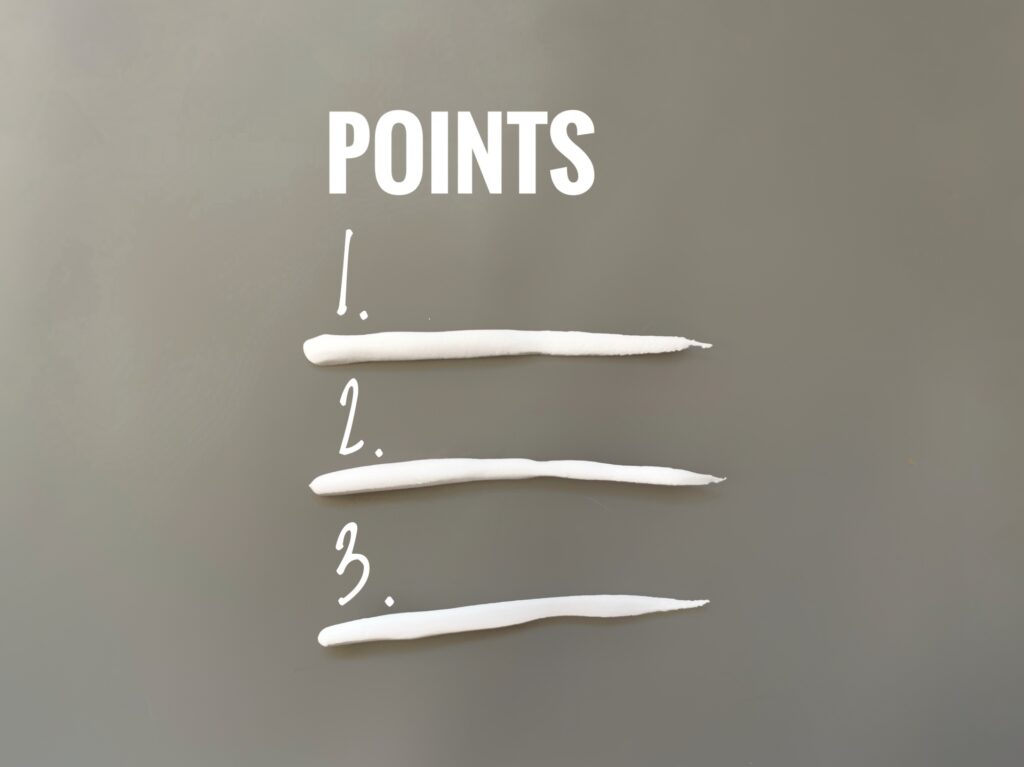
ケアマネの業務は、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成と、その管理・調整が基本です(介護保険法第7条の3)。仕組みをつくり、関係者をつなげる役割にあります。
依頼の内容が報酬の対象か、自立支援に結びつくかなど、判断基準を持つことが大切です。
業務内か業務外か、判断ポイントは3つ
- 制度上の業務か?(報酬対象になるか)
- その業務はケアマネ以外の専門職や家族で対応できるか?
- 本人の自立支援につながっているか?
また、記録として残すことも重要です。業務外と疑問視される依頼があった場合は、「記録に残しておく」「上司に相談する」ことで、トラブル回避にもつながります。
次に前項目の具体的な考え方について挙げています。以下の3点に留意して、その依頼は受けられるかどうか判断し対応しましょう。
- 「支援」ではなく「代行」になっていないかを見極める
- 曖昧になりやすい領域(医療連携、通院支援、生活支援)の役割は?
- 計画とのマッチング・説明責任・利用者本位の観点では?
ケアマネ自身ができる予防と対策とは

利用者さんからやってはいけないことを頼まれた際、断りきれずに悩むケアマネも少なくありません。
次に、予防と対策のポイントを紹介します。
契約時の「できること・できないこと」の明示
事業所として、利用者から業務範囲外のことを頼まれた場合の、ケアマネができること・できないことをマニュアル化して整理しておきましょう。マニュアルに従ってできること・できないこととその理由を丁寧に説明し、利用者や家族の理解を得るようにすれば、突然の依頼もなくなります。
定期的な説明と再確認
契約時だけでなくモニタリング時等にも「こういう行為はできない」と利用者や家族に定期的に説明・確認しておきましょう。
関係機関との連携強化、役割分担の共有
ケアマネジャーは、サービスの調整役なので多くの職種と関係性を持ちます。それぞれの役割分担は、家族や利用者本人も含めて担当者会議等で理解・納得を得るようにしておくことが重要になります。また、担当者会議などでの“お願いされやすい空気”を見直すことも必要です。
利用者・利用者家族は本当に困っていることも多くあります。できないからと突き放すのではなく、誰ならできるのかということを伝え、繋げてあげることが大切です。
事業所内での「相談しやすい環境づくり」
ケアマネジャーは、単独で利用者や家族と対面することが多く、その場での判断や返答を求められることも多いです。事業所では、「即返答をしない」ことをルールにし、一度持ち帰ることを厳守します。そして、部下が上司に困っていることを気軽に相談できる環境を構築してください。管理者やリーダーは部下に対して「叱責」ではなく「注意」をするように心がけましょう。
もし、あまりにも理不尽な依頼や明らかな悪意をもって無理難題を言ってくる場合は、事業所として行政などに相談しましょう。
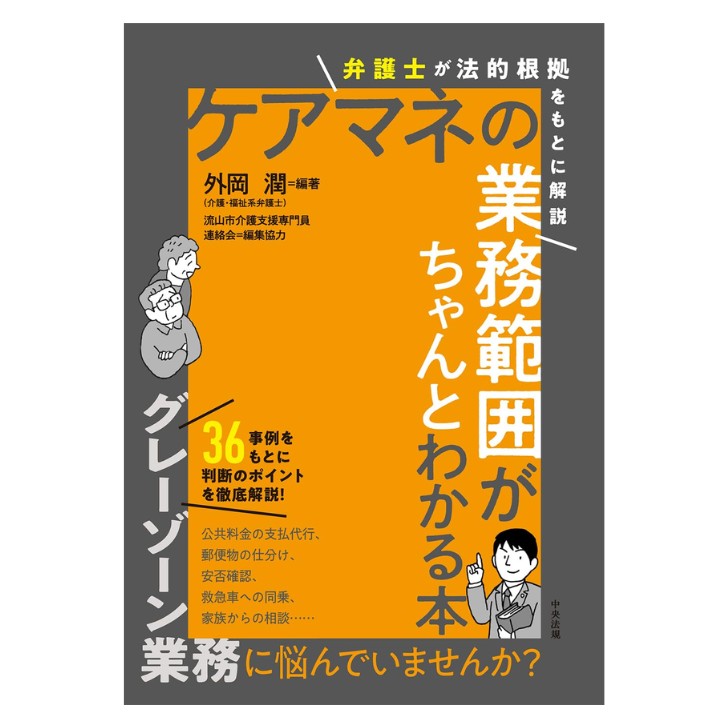
ケアマネの業務範囲がちゃんとわかる本
◆現場であるあるの36のグレーゾーン事例をもとに判断のポイントを解説!◆
現場で遭遇しがちな36事例を厳選し、その事例ごとに業務範囲をどのように判断すればよいのかを解説しています。公共料金の支払代行、買い物代行、安否確認、救急車への同乗、家族からの相談など……対応に悩みやすい場面での支援方法を、法的根拠をもとに具体的に指南します。
まとめ

ときに、ケアマネの業務は、介護保険とは別に利用者の生活全般をサポートしなければいけないような実態もあります。
しかしながら、「業務範囲外とされた業務について、誰がどのように対応し、その費用をどのように負担又は分担することが適切と考えられるか」については、社会全体で検討されなければなりません。
実は、ケアマネが『なんでもやってくれる便利な人』だと思われる背景には、制度の難解さや現場の人手不足などの社会問題も原因の一つです。 ただ、その中でも自分の役割を明確にし、本来の業務に集中することでより質の高い支援に繋がっていくに違いありません。
「断ること=冷たい」ではありません。「断ること=自分を守ること」であり、「サービス全体を守ること」でもあります。断る勇気は専門職の資質です。「何でもやってあげる」ケアマネジャーではなく、ケアマネジャーの専門性を理解してマネジメントすることが重要です。
今後も、ケアマネが専門性を発揮し持続可能な支援体制を築くために、まずは【業務の線引きをしっかり持つこと】を忘れずに、日々の業務頑張っていきましょう。
投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。
最新の投稿
 居宅介護2025年8月28日ケアマネ試験まで残り2か月!直前期にやるべき合格対策とは
居宅介護2025年8月28日ケアマネ試験まで残り2か月!直前期にやるべき合格対策とは 居宅介護2025年7月22日ケアマネが辞めていく理由とは?人材不足にストップをかける5つのヒント
居宅介護2025年7月22日ケアマネが辞めていく理由とは?人材不足にストップをかける5つのヒント 居宅介護2025年5月26日ケアマネは何でも屋?業務範囲外の依頼の向き合い方とは
居宅介護2025年5月26日ケアマネは何でも屋?業務範囲外の依頼の向き合い方とは 通所介護2025年5月8日「通所介護サービス提供体制強化加算」の効果的活用法とは?
通所介護2025年5月8日「通所介護サービス提供体制強化加算」の効果的活用法とは?


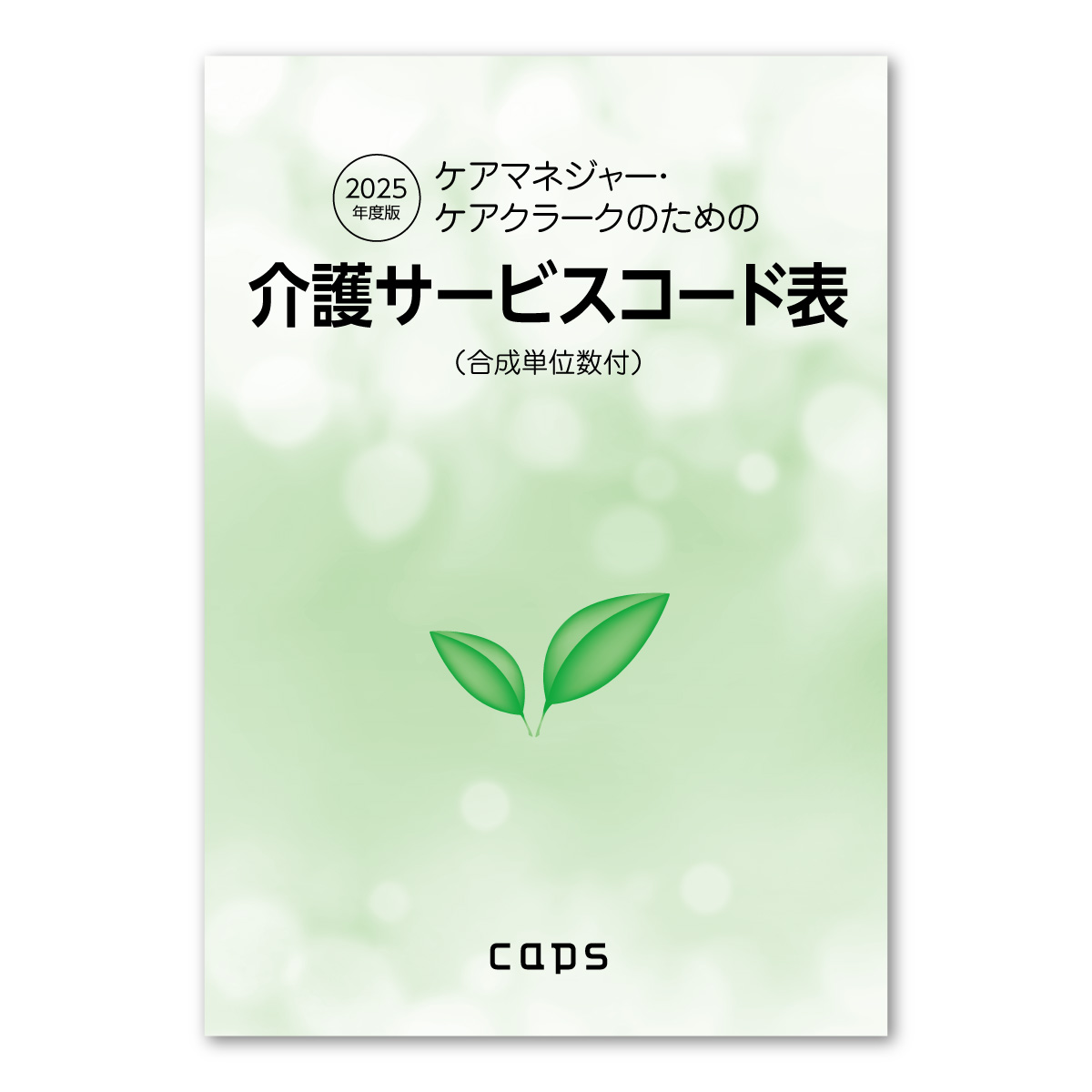
.jpg)
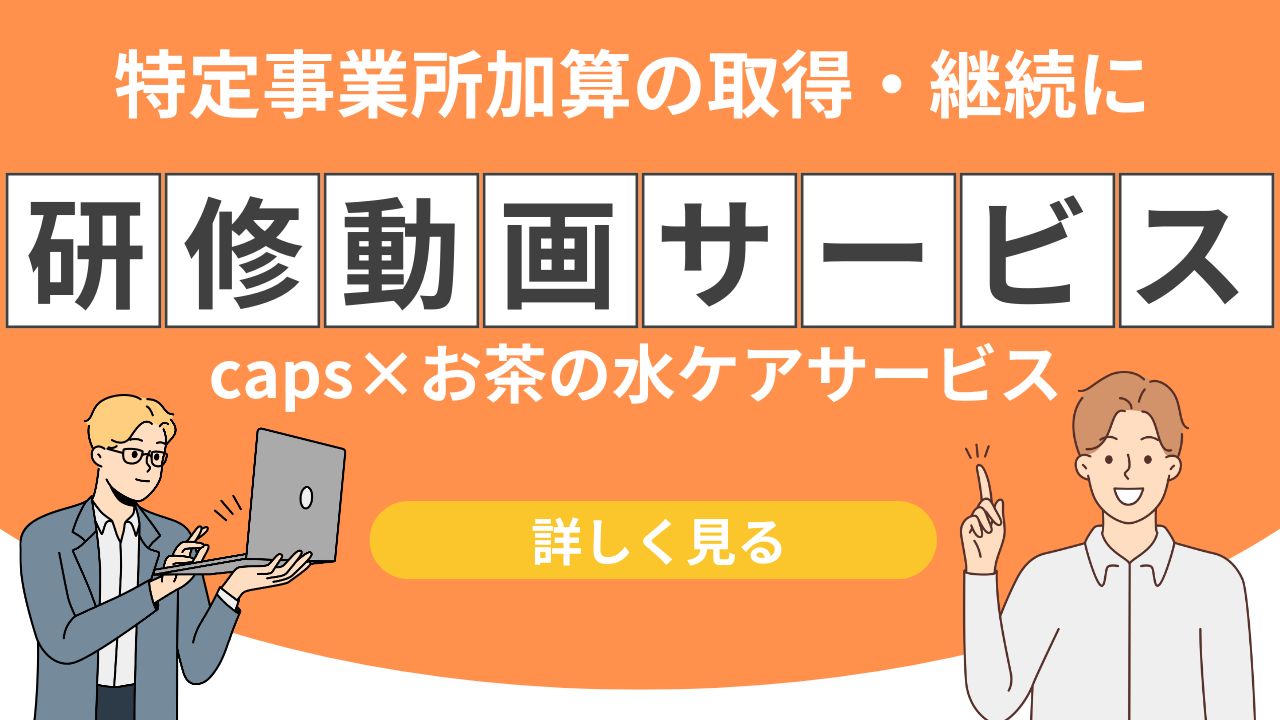

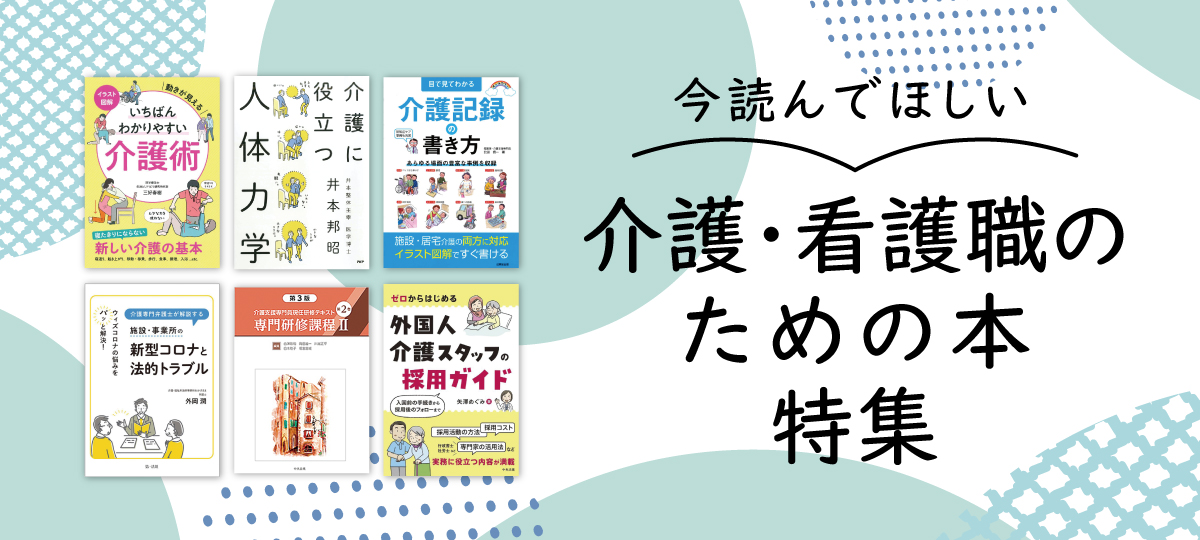
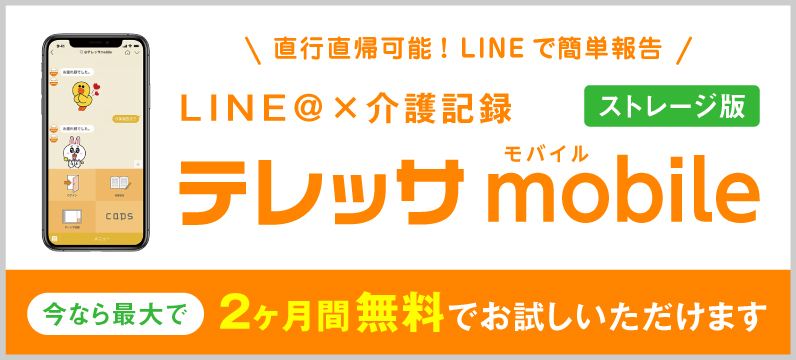

コメント