ケアマネは何でも頼まれがちですが、その中でも、やってはいけないことが多くあります。
ケアマネは介護保険法第7条第5項に定義された、要介護者又は要支援者からの相談に応じる相談援助専門職であり、職業倫理に基づく行動が強く求められています。
今回は、介護保険制度のおさらいと、ケアマネの役割、やってはいけないことについて、一緒に考えてみましょう。
ケアマネの役割と守るべきこと

まずは、今一度、ケアマネの役割と守るべきことについて確認しておきましょう。
ケアマネの役割
ケアマネ(介護支援専門員)は、就業する場所によって呼称が異なります。
- 居宅ケアマネ(介護支援専門員)・・・在宅で生活する利用者を対象
- 施設ケアマネ(介護支援専門員)・・・施設に入所する利用者を対象
利用者の生活する場所がどこかによって、ケアマネの業務内容や業務量が変わることがありますが、基本的に役割は同じです。
- 介護(支援)認定申請に対する協力・援助
- 居宅・施設サービス計画の作成
- 他サービス業者との連絡調整
- サービス実施状況の把握・評価
- 市町村等行政関係、及び、主治医や医療関係との連絡調整・連携
- 利用者、家族との信頼関係構築・連携
- 相談業務
ケアマネの守るべきこと
人権の尊重
利用者の個人の尊厳の保持を第一とします。利用者の基本的人権を擁護し、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように、利用者本位の立場から支援をします。
公正・中立な立場の堅持
利用者の利益を最優先し、特定のサービス種類、特定の事業所・施設の利益に偏ることなく活動します。
秘密保持
業務に関して知り得た、利用者や関係者のプライバシーを守ります。もちろん、就業中、及び、その職を離れて以降も同様です。
他職種等との連携
利用者が、住み慣れた地域で継続した生活ができるように、関係市町村や地域の保健・福祉・医療サービス等と連携を図り、総合的なサービスの提供を行います。
資質の向上
ケアマネには期間ごとの更新制度が設けられています。多様な相談に相対するため、介護保険以外の知識が必要なことも多いです。自身の資質向上は、全体の資質向上、ひいては要介護者等の環境改善に繋がります。
これらは、ケアマネがマネジメントを実施するにあたり、いつも心に留めておかなければならない基本です。(*ケアマネには他に法令遵守、説明責任、地域包括ケアの推進、社会的信頼の確立などが守るべき倫理としてあります。日本介護支援専門員協会の倫理綱領を参考にしてみてください。)
ケアマネがやってはいけない!?こんな時どうする?

前章の『ケアマネの守るべきこと』を念頭において、私が、これまでに「これは、やってはいけない」と思ったことを簡単に事例として挙げてみました。おそらく、ケアマネの経験がある方は、似たような経験をお持ちではないでしょうか。
事例1
ケアマネのAさんは、骨折後退院することになったCさんのサービス計画に、住宅改修と通所のデイケアを導入したいと考えました。それをCさんに話したところ、とても険悪な雰囲気になってしまいました。Cさんは、亡くなったご主人が建てた古い家をとても大切にしていたのです。
事例2
その居宅介護支援事業所は、デイサービスや訪問介護、サービス付き高齢者住宅等を併設する法人の一事業所です。最近、法人から各事業所に収支のバランスについて指示が出たらしく、ケアマネのHさんは、管理者からヘルパーやデイサービスを利用するなら同法人の事業所を使うように言われました。Hさんは、その方針に違和感がありました。
事例3
ケアマネのⅯさんが、友達とファミレスで食事をしていたら、後ろの席から自分の担当の利用者の名前が聞こえてきました。「?」と思っていたら、その声は、Ⅿさんが計画書の中で位置づけしているサービス事業所の職員でした。店内に、人は多くなかったのですが、Ⅿさんは気が気ではありませんでした。
事例4
会議を終えたケアマネのYさんは、他のケアマネから声をかけられました。計画書の内容や、位置づけしている事業所のことなどについての批判でした。Yさんは、ご利用者やそのご家族の意向をもとに計画を立てたので、なぜそのようなことになってしまうか分からず、とても困ってしまいました。
事例1は、人権の尊重です。自己選択・自己決定は何よりも優先されるべきことです。
事例2は、公正・中立です。そして、ここにもやはり、利用者の人権が重要課題としてあります。
事例3は、守秘義務です。誰かに聞いてほしいことや、相談したいこともいろいろあると思います。ただし、対人援助職には、全て、守秘義務が課されていることを忘れてはいけません。
事例4は、多職種連携に関わります。他者の計画や事業所を批判しては、チームが稼働しません。
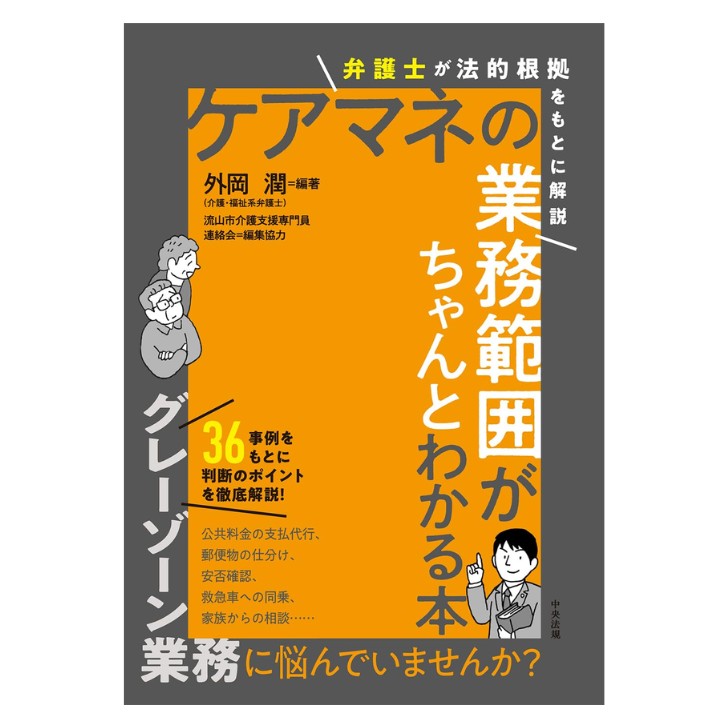
ケアマネの業務範囲がちゃんとわかる本
◆現場であるあるの36のグレーゾーン事例をもとに判断のポイントを解説!◆
現場で遭遇しがちな36事例を厳選し、その事例ごとに業務範囲をどのように判断すればよいのかを解説しています。公共料金の支払代行、買い物代行、安否確認、救急車への同乗、家族からの相談など……対応に悩みやすい場面での支援方法を、法的根拠をもとに具体的に指南します。
まとめ
介護保険法上の全てのことに関して、利用者、及び、家族にその選択権と決定権があります。例えば、ケアマネが、その専門性において別のサービスに有効性がある、と考えたとしても、利用者本人やその家族が選ぶものを優先すべきです。 ケアマネが、利用者に不利益が生じると考えた場合は、利用者や家族としっかり検討します。このプロセスが利用者・家族の信頼関係の構築に役立ちます。
また、ケアマネは個人で動くことが多いですし、その場で即座に答えを出さないといけない場合もあります。それが正しかったのか?他に答えは無かったのか?不安になることも一杯です。
事例1〜4についても、とるべき手段は、皆さん個々の環境や考え方で違うかもしれません。
ただし、忘れてはいけないことは、ケアマネには守らなければならないことがある、ということです。
今、ケアマネである方、これから資格を取ってケアマネになろうとしている方、ぜひ、この機会にもう一度、ケアマネの業務範囲を見直してみましょう。
投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。
最新の投稿
 居宅介護2025年8月28日ケアマネ試験まで残り2か月!直前期にやるべき合格対策とは
居宅介護2025年8月28日ケアマネ試験まで残り2か月!直前期にやるべき合格対策とは 居宅介護2025年7月22日ケアマネが辞めていく理由とは?人材不足にストップをかける5つのヒント
居宅介護2025年7月22日ケアマネが辞めていく理由とは?人材不足にストップをかける5つのヒント 居宅介護2025年5月26日ケアマネは何でも屋?業務範囲外の依頼の向き合い方とは
居宅介護2025年5月26日ケアマネは何でも屋?業務範囲外の依頼の向き合い方とは 通所介護2025年5月8日「通所介護サービス提供体制強化加算」の効果的活用法とは?
通所介護2025年5月8日「通所介護サービス提供体制強化加算」の効果的活用法とは?


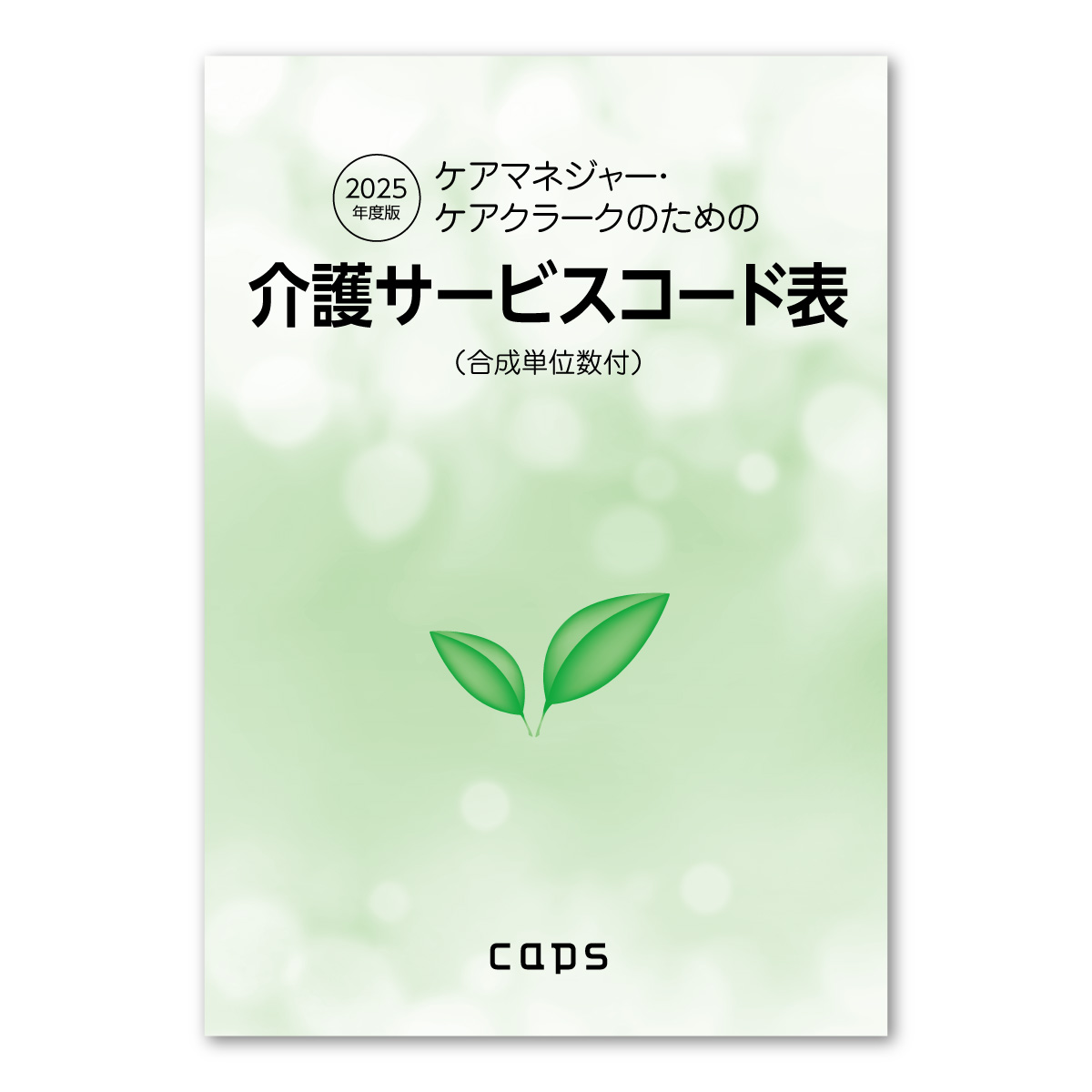
.jpg)
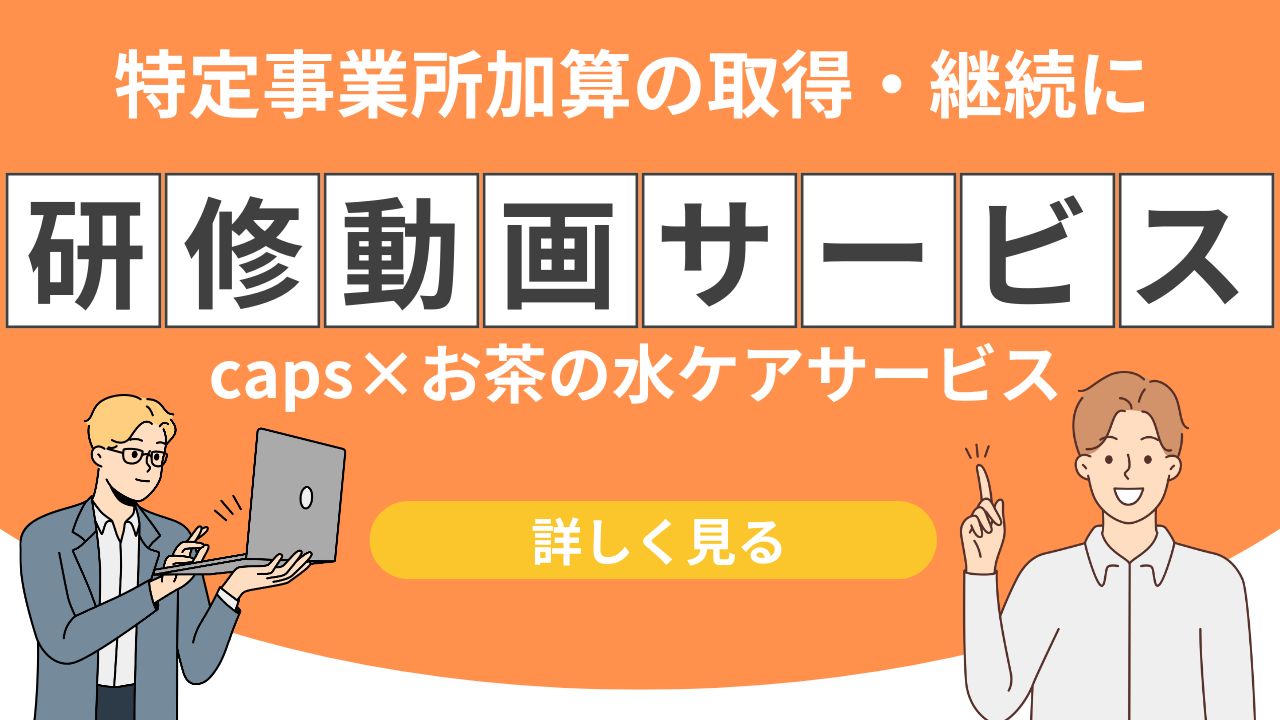

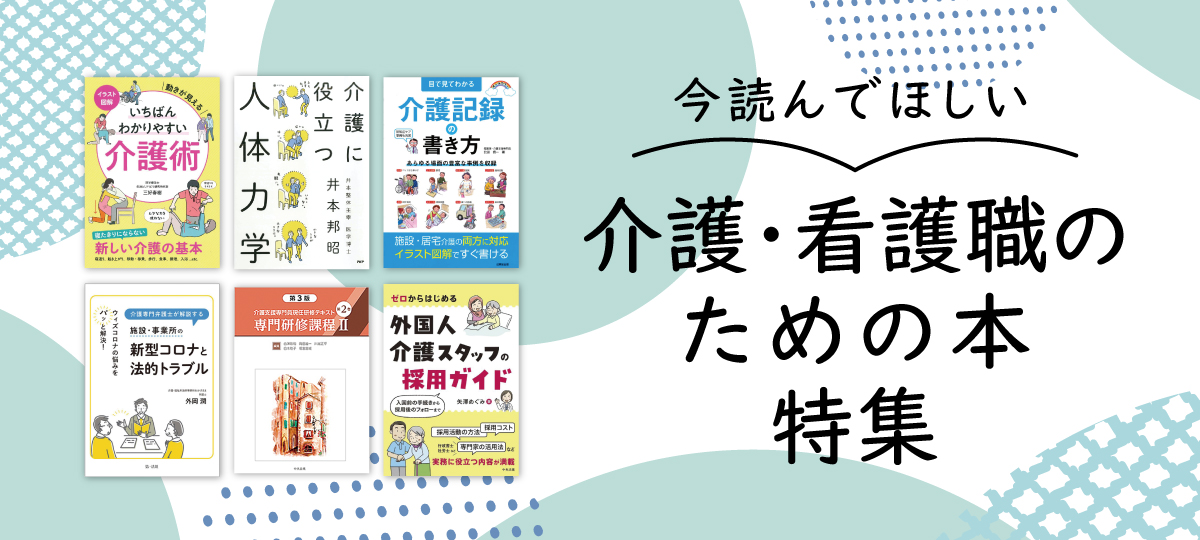
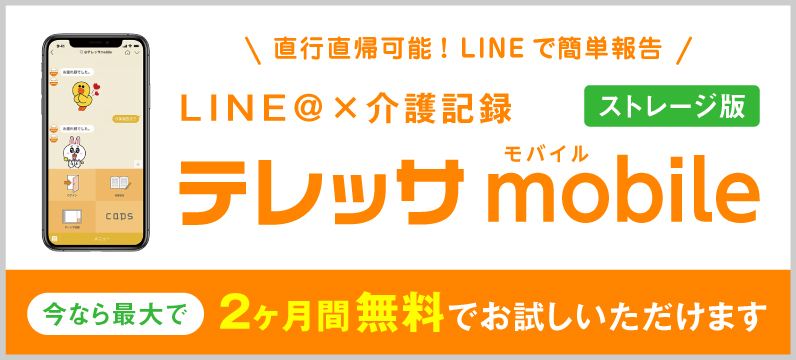

コメント