看護師や介護福祉士などの国家資格を保有する方で、病院や介護施設ではなく、子どもへの支援ができる分野で働きたい!と希望されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、子供の療育のために児童発達支援事業所や放課後等デイサービスを探しているという方もいらっしゃるでしょう。
今回は、そんな方に向けて、児童発達支援や放課後等デイサービスについて解説します。
児童発達支援や放課後等デイサービスとは何か、その違い、働いている方の資格などについてお話します。
ご興味をお持ちの方は、ぜひ参考にしてくださいね。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違いとは
どちらも児童福祉法に定める、発達に心配のある児童を療育する通所サービスです。
両者の違いは対象年齢にあり、「児童発達支援」は、0~6歳までの未就学児を、「放課後等デイサービス」は、6~18歳の小学校入学から高校卒業までを対象にします。
私の経験から言うと、「児童発達支援」は1対1の個別療育を、「放課後等デイサービス」は小集団での療育を行っている事業者が多いのが特徴です。
児童発達支援で行う療育とは
児童発達支援は、就学前の障がいのある子供、発達に心配のある子供に対し療育を行う通所サービスです。
療育内容としては、トイレや着替えなど日常生活の動作指導や集団生活への適応訓練、運動訓練や言語訓練などを行います。
2012年の児童福祉法改正後から、児童発達支援の対象に「発達障がい」も含まれるようになりました。
発達障がいのある子供が児童発達支援の対象になったことで、利用者数が急激に増加しており、児童発達支援の事業所が足りていないのが現状です。
乳幼児期は身体面も認知面も急速に発達する時期であり、早期介入が望ましいとされているにも関わらず、受け皿が不足している現状は問題だと言わざるを得ません。
放課後等デイサービスで行う療育とは
放課後等デイサービスは、就学児が放課後や夏休みなどの長期休暇に通所して療育を受けるサービスです。
放課後等デイサービスでは、自立した日常生活を営むために必要な訓練を行い、創作的活動や作業活動、地域交流の機会の提供などを行います。
放課後等デイサービスでは、学校と支援の一貫性が図れるように、学校と連携・協働してサービスを提供していくことが重要です。
勉強についていけなかったり、先生やクラスメイトと上手くコミュニケーションが取れず、学校になじめなかったりする子供はたくさんいます。
放課後等デイサービスは、小集団での療育を通して社会に適応していくための訓練を行う必要不可欠な通所サービスです。

発達障害児のための生活リズムボード
ADHDや自閉症などの発達障害を持つ子供は、目から入る情報のほうが理解しやすいという特徴があります。
生活リズムボードは「やるべきこと」「できたこと」が視覚でわかり、楽しみながら「お支度」ができるようになります。
また、1週間のスケジュールや曜日感覚など、身に着けて欲しい内容がぎゅぎゅっと詰まった1枚です。
児童発達支援や放課後等デイサービスの共通点とは

共通点は、保護者支援が重視されることです。
身体や知的、発達や難聴など様々な障がいを持つ子供の保護者の不安は大きく、悩みは尽きません。
寄り添い、親身に相談に乗ってくれる存在が必要不可欠です。
児童発達支援や放課後等デイサービスの職員は保護者への支援を忘れてはならず、保護者の意向なども聴取した上で個別支援計画を組み立てます。
さらに、児童発達支援や放課後等デイサービスは、保護者に息抜きの時間を与えるレスパイトケアも行います。
児童発達支援や放課後等デイサービスは、保護者への相談支援やレスパイトケアといった役割が非常に大きいのです。
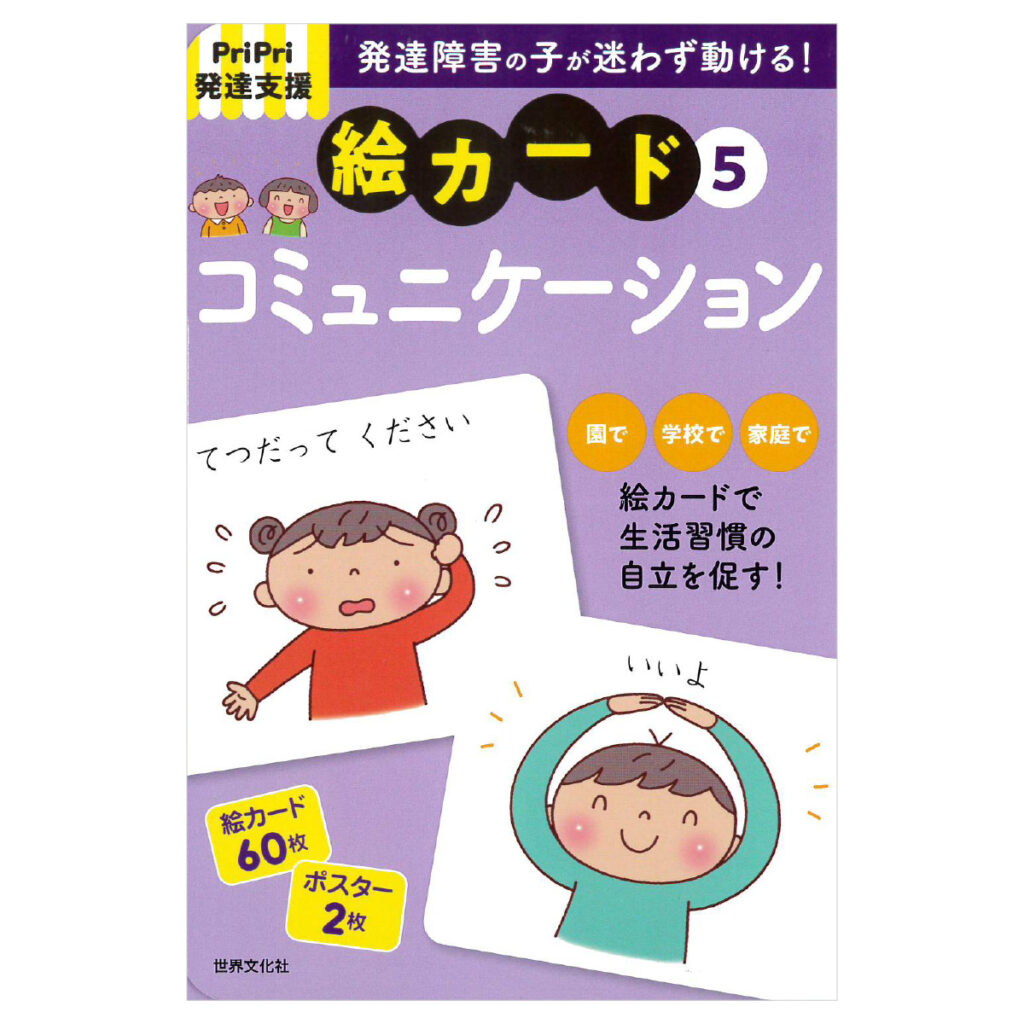
発達障害の子が迷わず動ける!絵カードシリーズ
絵カードで生活習慣の自立を促す人気のシリーズです。
集団生活・着替え・コミュニケーションなど、お子さまの「苦手な部分」に対し、絵カードを使って学んでいくことができます。
児童発達支援や放課後等デイサービスで働いている人が持つ資格とは

両者とも、「児童発達支援管理責任者」「指導員または保育士」「機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)」の配置が必須であるとしています。
さらに、重症心身障害のある子どもに対して児童発達支援や放課後等デイサービスを行う場合は、 指導員に代えて児童指導員、さらに嘱託医、看護師、機能訓練担当職員の配置を行い、医療的ケアの体制を整える必要があるとされています。
そのため、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」には、それらの資格を有する方が勤務しています。
児童発達支援管理責任者とは
ここからは児童発達支援管理責任者を目指す方に向けてまとめています。
児童発達支援管理責任者は、子どもごとに個別支援計画を作成し、提供サービスの管理を行います。さらに、他の職員に対して指導・助言を行ったり、実際に現場でサービス提供に当たったりすることもあります。
児童発達支援管理責任者は、子どもや保護者の意向を聴き、個々の障がい特性に応じた支援計画を作成しなければならず、専門性の高い職種と言えるでしょう。
児童発達支援管理責任者は、障害児通所支援事業所等ごとに1名配置することが義務付けられています。
■児童発達支援管理責任者になるためには
児童発達支援管理責任者になるためには、実務要件と研修をクリアしなければなりません。
実務要件は以下の3パターンです。
- 相談支援業務5年以上
- 直接支援業務8年以上
- 国家資格等が必要な業務5年以上+相談支援業務または直接支援業務3年以上(国家資格等が必要な業務と同時期でも可)
実務要件の次は以下の3つの研修を修了する必要があります。
- 基礎研修
- OJT(職場で実務をすることで職業教育をする現任研修)
- 実践研修
児童発達支援管理責任者になった後も、5年ごとの更新研修が必要です。
看護師や介護福祉士、社会福祉士などの資格を有し、5年以上その職に従事していれば、たいていの場合実務要件はクリアしていると考えられます。
3段階の研修が難問ですが、それくらい児童発達支援管理責任者には、高い専門性が求められているということになります。
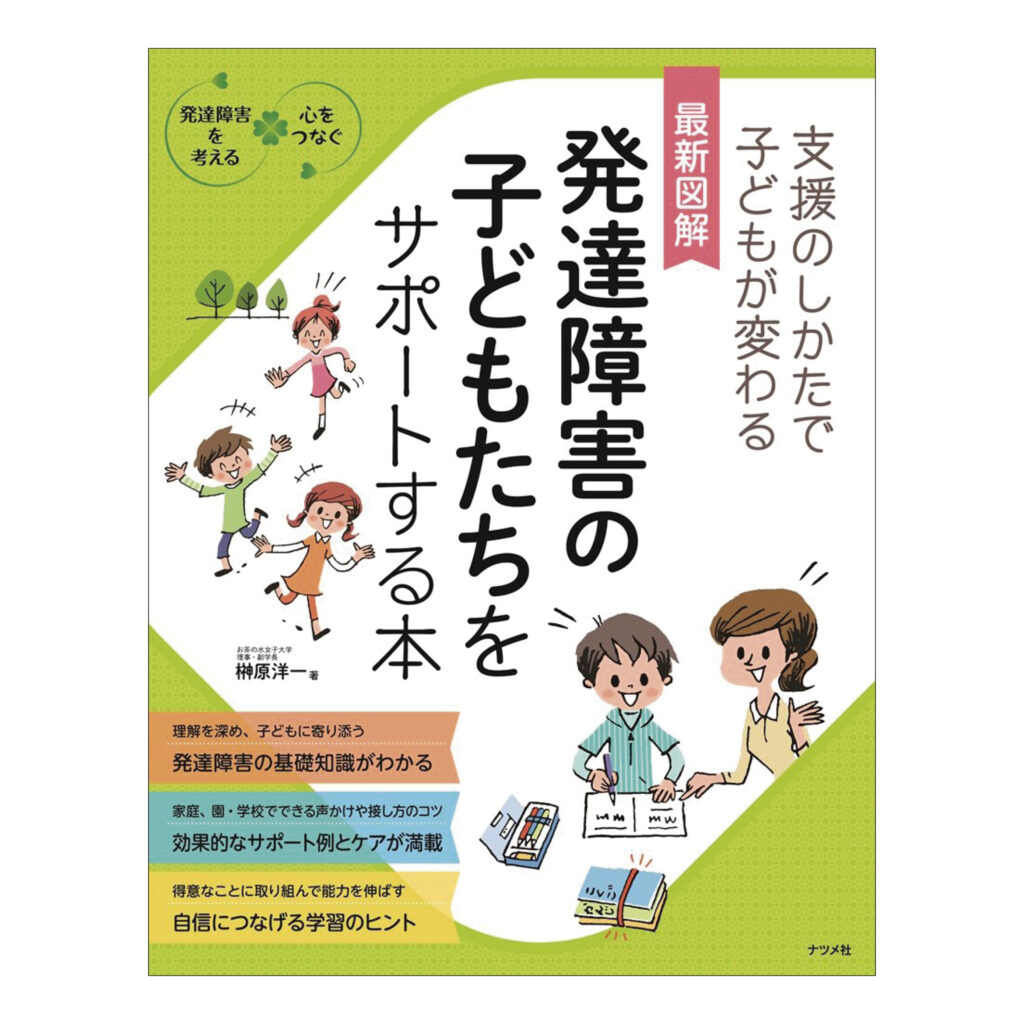
発達障害の子どもたちをサポートする本
理解を深め、子どもに寄り添う1冊。
発達障害の基礎知識、家庭・園・学校でできる声かけや接し方のコツがわかる!効果的なサポート例とケアが満載です。
得意なことに取り組んで能力を伸ばす、自信につなげる学習のヒントが詰まっています。
児童指導員や指導員、機能訓練担当職員について
児童指導員には、社会福祉士や精神保健福祉士、小・中・高等学校の教諭資格を有する者のほか、大学等で社会福祉学や心理学、教育学の課程を修了した者もなることができます。
指導員には資格要件は特にありません。
機能訓練担当職員は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、心理指導担当職員等の資格が必要です。
まとめ:専門職は児童福祉の分野でも働けます!

近年、自閉症スペクトラム障害やADHDなどの発達障がいの認知度が上がり、早期に発見し、早期に療育につなげる流れになっています。
しかし、発達障がいのスクリーニングをして療育を必要とする子どもたちを増やすだけ増やして、その療育環境を整えられていないのが現実です。
受け皿となる事業所の数や職員が足りず、療育の質の担保が充分でない、待機児が多いなどの問題が起こっています。
今後まだまだ事業所の数は増え、従事する人材も求められる児童福祉の分野。
子どもの未来に携わる分野に従事したいと希望されている専門職の皆さん、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの事業所も、やりがいは大きいのではないでしょうか。
投稿者プロフィール

- 看護師・保健師としての経験後、現在は高齢者のケアマネジメント業務に奮闘中。ベビーから高齢者の方まで幅広く関わっています。
最新の投稿
 訪問介護2024年6月27日介護職員の資格一覧!ホームヘルパー1級・2級との違いも解説
訪問介護2024年6月27日介護職員の資格一覧!ホームヘルパー1級・2級との違いも解説 訪問介護2024年4月11日軟膏塗布や在宅酸素などに関わる行為はヘルパーが実施可能?実施可能な範囲について解説!
訪問介護2024年4月11日軟膏塗布や在宅酸素などに関わる行為はヘルパーが実施可能?実施可能な範囲について解説! 児童福祉2023年9月13日発達障がいやグレーの児のスケジュール管理に生活ボードがおすすめ
児童福祉2023年9月13日発達障がいやグレーの児のスケジュール管理に生活ボードがおすすめ 訪問介護2023年7月13日在宅での看取りの現状と問題点は?ケアマネが行うべき支援について教えます
訪問介護2023年7月13日在宅での看取りの現状と問題点は?ケアマネが行うべき支援について教えます



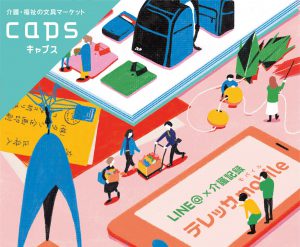
.jpg)
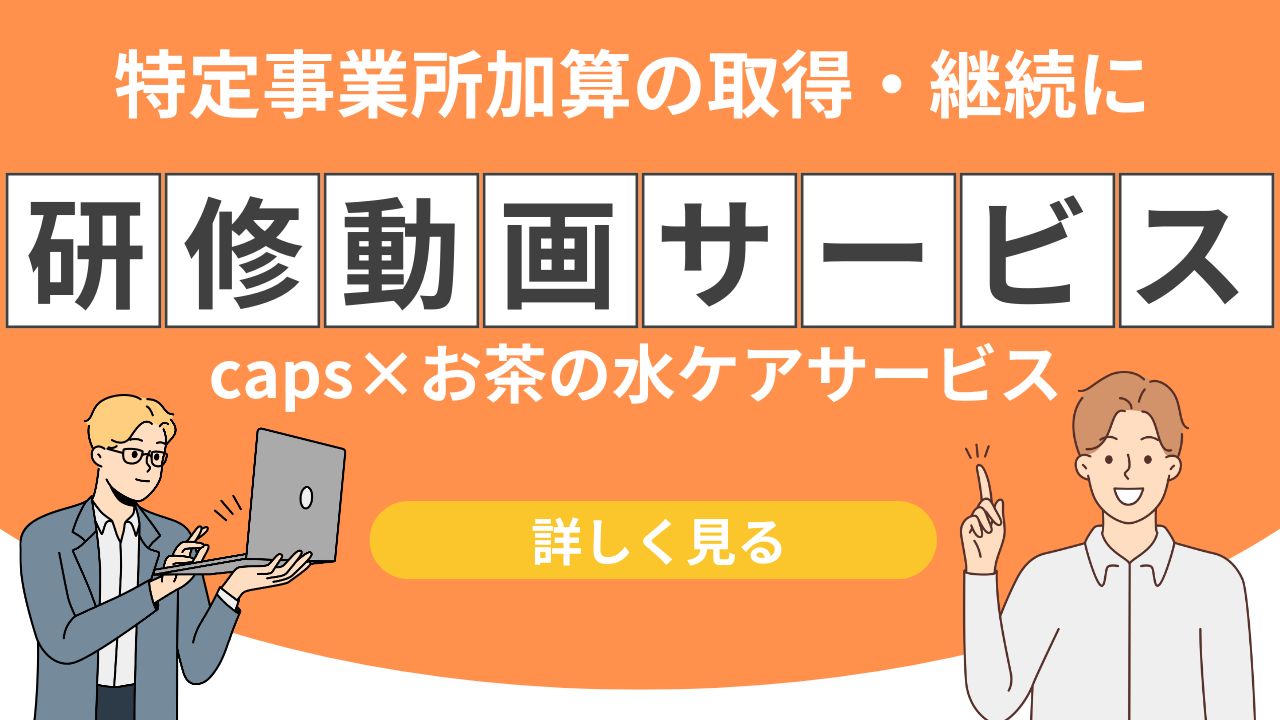

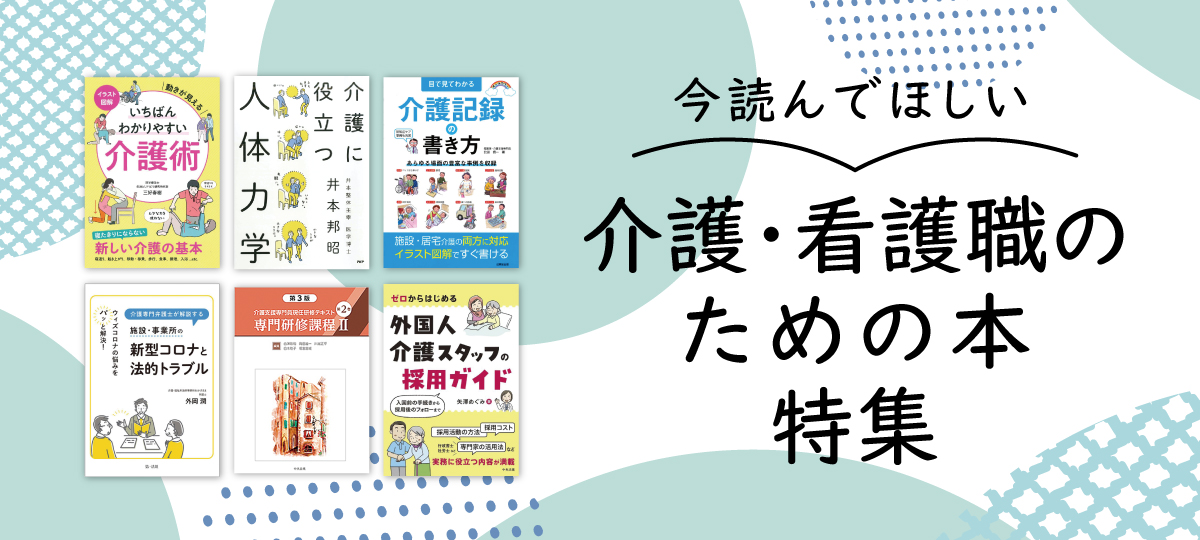
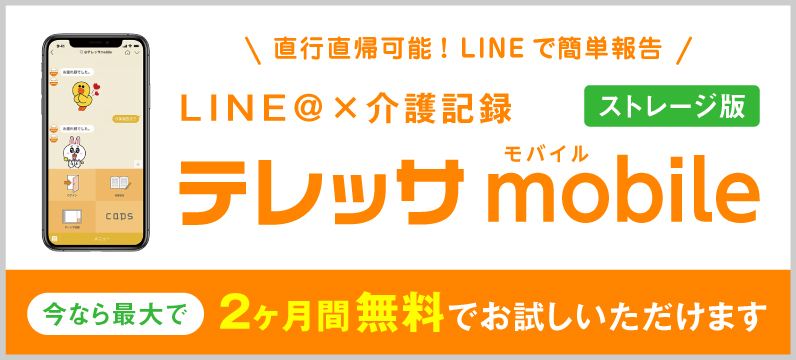

コメント