訪問看護には、できること、できないことがあり、介護職の仕事との切り分けが難しい部分もあります。
ご利用者様に業務外のことを頼まれて、断り切れなかったことはありませんか?
筆者が所属していた訪問看護事業所では、「買い物を頼まれた」「ゴミ出しを頼まれた」ケースなどがあり、訪問看護サービスの内容について話し合われたことがあります。
今回は、実際にあった事例を取り上げました。一緒に考えていただけませんか?
訪問看護とは|できるサービス・できないサービス
訪問看護とは、医療的なケアが必要な利用者の自宅に看護師等が訪問し、治療やケアを行うサービスです。
訪問看護では、以下の内容を行うことができます。
- バイタル測定・健康状態の管理
- 医療処置
- お薬の管理・相談
- 療養生活の相談・支援
- 身体の衛生管理・日常生活の支援
- 終末期ケア・緩和ケア
- 医療機関との連携
- リハビリテーション
一方で、買い物や調理などの「家事」にあたることは訪問看護では行うことができません。
しかし、おむつ交換など、訪問介護と訪問看護の両者で行える内容もあり、利用者側からすると頼めることと頼めないことが不明瞭であったり、「これぐらいならやってもらえるだろう」という気持ちになってしまう部分もあるでしょう。
訪問看護の具体例|できること?できないこと?

ご利用者様が「訪問看護師に頼んだ買い物」のエピソードをお伝えします。
※ご利用者様の個人情報保護の観点から情報を一部変更しました。
■ 訪問看護内容ではないことを頼まれたエピソード
6年くらい前のエピソードです。
同僚看護師Xが、Aさん宅を訪問したのは寒い冬の午前中でした。
ご利用者様のAさんは、50代男性、脳梗塞・右半身まひ。歩行時には杖や歩行器が必要で、横になって過ごすことが多く、一人で長距離は歩けません。
看護とリハビリを行うため伺っていました。
【看護師 X】「Aさん、おはようございます!お邪魔します」
と、訪問すると
【Aさん】「寒いなぁ、肉まん食べたい」「買ってきて」
【看護師 X】「寒いし、肉まん食べたくなりますよね」「でも私たちは買い物に行けなくて…。ごめんなさい。」「事業所に帰ったら、またケアマネさんに相談してみます」
看護師 Xが説明はするものの、Aさんは少しムッとした様子。いつもより会話も少なめです。
食べたい肉まんを「買ってきてもらえない」ことが引っかかったようです。
幸いにも、Aさんは看護サービスを拒否することはなく、爪切りなどのケアを受け、室内での可動域運動や家周りでの歩行訓練を行いました。
その後、看護師Xは、「自分の対応はこれで正解だったのか」と自問します。食べたいものを自由に食べられないもどかしさがある利用者様、それを「業務外」だからと断るだけでよかったのでしょうか。
その日の夕方、事業所に戻った看護師Xは、同僚に相談、カンファレンスを行うことに。
カンファレンスの結果、2〜3日後に訪問予定の理学療法士Yが、お試しという形で「リハビリを兼ねた買い物」案を提案。理学療法士Yは、管理者の許可を得て、危険がないよう入念に計画することになりました。
理学療法士Yの訪問日、理学療法士YがAさん宅を訪問し、お試しでリハビリを兼ねた買い物に行くことを提案すると、Aさんは嬉しそうにしていたそうです。
歩行訓練を兼ねてコンビニへ向かったAさん。念願のホカホカ肉まんを買え、キラキラの笑顔が浮かんだそう。
家にいることが多いAさんにとって、自分でお店へ行けた達成感や商品を選ぶ喜びは計り知れないでしょう。
しかし、結果、訪問時間オーバーで、訪問看護としてはその後も継続することは叶いませんでした。
ケアマネージャーにも相談し、今後は買い物など、何かあればホームヘルパーさんにお願いすることになりました。
Aさんはその後、訪問看護としてもきちんと対応を考えたことでケアマネやホームヘルパーとの連携を理解し、看護師に買い物を頼むことはなくなりました。
■ エピソードの対策で良かった点/反省すべき点
▶ 良かったと思う点
①事業所での話し合い・報告と相談
➁他業種との連携
③個人の楽しみ・生活の質を考えた対策と計画
④ご利用者様への説明とご理解
⑤チーム協力体制の強化
⑥問題の共有、対応の統一化
継続は叶わなかったけれど、Aさんの希望とサービス内容をうまく掛け合わせることで、可能性を見出せ、Aさんも納得していただけたことは事業所として一歩前進できたエピソードです。もし、看護師Xが事業所に相談していなければ、計画は無かったでしょう。
また、Aさんの理解が得られないまま、ただ断わるというだけの対応では、Aさんの不満や不信感が募っていたかも知れません。
逆に、緊急性のない事柄で、単独判断で良かれと思って買い物に行っていたとしたら、「あの人は買ってきてくれたのに」と、他の同僚とAさんの関係や同僚同士の関係が崩れたり、訪問看護の業務内容が曖昧になり、「行うべきこと」に注力できないということも起こったかもしれません。
▶ 反省すべき点
反省すべき点としては、そもそもAさんは、介護職と看護職の業務内容の違いを把握されていなかったという点です。
「私たちは買い物に行けない」と伝えたものの、Aさんのなかでは疑問が生じます。サービスの利用時に、しっかりと理解していただけるまでお伝えできていなかった可能性もありますが、看護師ひとりひとりが「できること・できないこと」について、明確な内容と、なぜできないのかということを理解し、きちんと伝えることができるかということも大きく関わってくると感じています。
しかし、ご自宅で過ごされているのであれば、ご利用者様の楽しみもあって良いのではないかという点もあります。在宅で過ごすことを多方面からサポートするのが私たちの仕事です。あらゆることを想定して、事業所、関係者で話し合うことが重要です。
看護職ができる業務|介護職ができる業務

ここで、介護業務と看護業務を比べてみます。
訪問介護は、居宅で日常生活上のお世話を行うサービス。
訪問看護は、医師の指示のもと居宅で療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。
■看護職ができる業務とできない業務
| 看護職ができる 身体介助 | 看護職ができない 生活介助 |
|---|---|
| 食事介助 排泄介助 清拭・入浴 体位変換 移動介助 服薬介助 ※吸引・経管栄養など (※は喀痰吸引等研修修了者) | 掃除 洗濯 ベッドメイク 衣服の整理 一般的な調理 配膳・下膳 買い物 薬の受け取り など |
■介護職ができる業務「原則として医行為ではないと考えられるもの」
介護職と看護職が「できること・できないこと」をはっきり線引きすることは難しい部分もあります。
看護職ができる業務については前述のとおりですが、介護職ができる業務とは「原則として医行為ではないと考えられるもの」となります。
「原則として医行為ではないと考えられるもの」とは、体温測定や血圧測定、パルスオキシメーターの使用、健康な爪の爪切り、重度の歯周病などがない口腔ケア、医薬品の取り扱い、市販の浣腸薬などが含まれます。
【参考・引用元】医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
しかし、高齢者介護や障害者介護の現場でおこなわれる「原則として医行為ではないと考えられるもの」の業務判断は、ケースバイケースで現場判断と受け取れます。
ご利用者様やご家族から見ると、「同じことをしているのに、なぜこれはダメなの?」と、思われることもあるかもしれません。判断に迷う場合は必ず事業所や関係者に確認しましょう。曖昧な状態で「良かれと思って」対応するのは後々トラブルに発展することがありますので注意が必要です。
まとめ
ご利用者様に頼まれたことが「訪問看護内容ではないこと」である場合、その都度、訪問看護内容などが書かれた分かりやすいパンフレットを利用して理由を丁寧に説明する、ご利用者様や家族の悩みを知る、事例や対策を共有し、事業所として統一した対応を行う、、そして、良好な信頼関係を継続することといったことが重要となります。
「ゴミ捨てを頼まれる」ケースなどは、ゴミ捨て場が訪問後に通るところにあるならば、臨機応変に出しても良いと個人的には思います。
しかし、考え方はさまざまなので、「事例や対策を共有し、統一した対応」が大切であると思います。
ご利用者様やご家族は、一人でストレスを抱えているケースが多いですから、訪問者に悩みなどの思いを伝えられることは良い関係であると言えるでしょう。
悩みが分かることで、寄り添った看護提供をしやすくなります。
居宅で安心してすごしていただくためにも、受け取った悩みは、事業所の仲間と共有し考え、チームでより良い看護を提供したいですね。
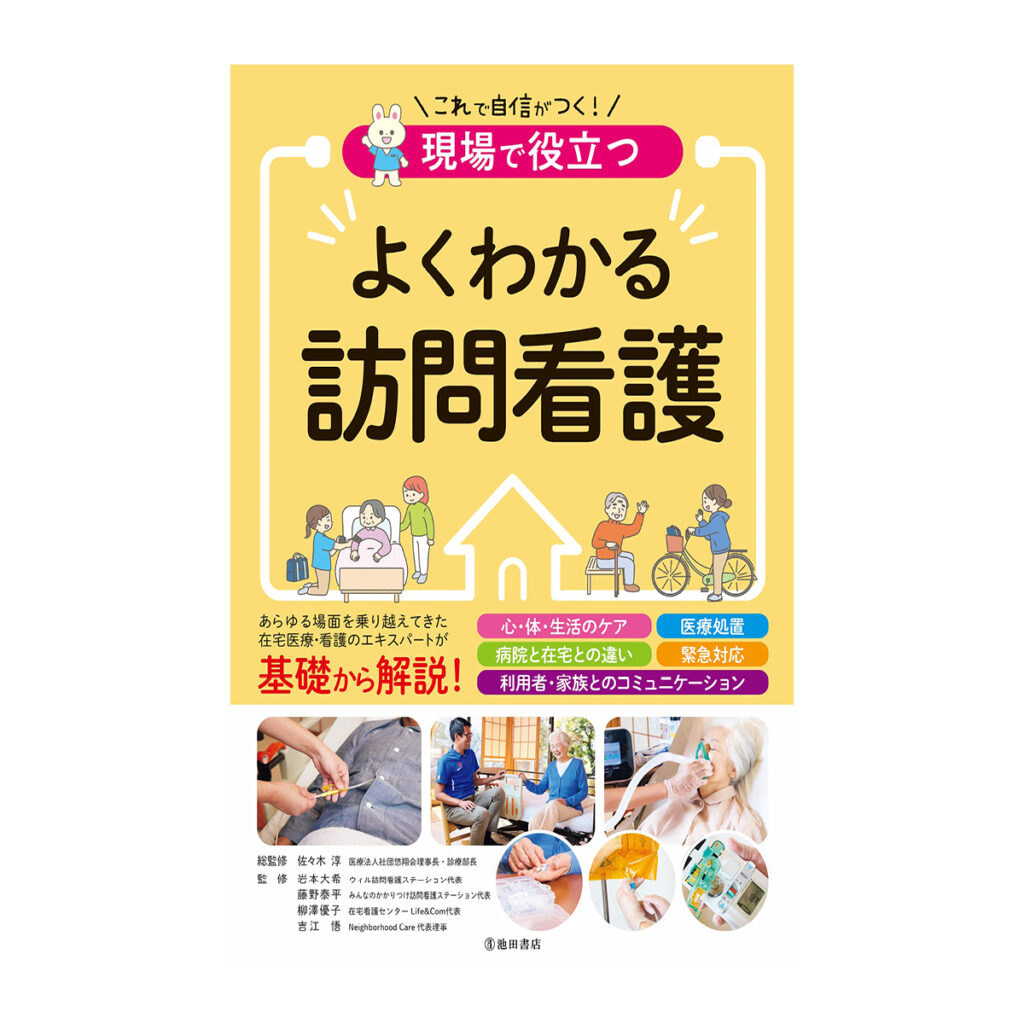
現場で役立つ よくわかる訪問看護
あらゆる場面を乗り越えてきた訪問看護のエキスパートが、心・体・生活のケア、医療処置、緊急対応、病院と在宅との違い、利用者・家族とのコミュニケーションなどについて、基礎から解説。
写真とイラストでわかりやすく、実例も紹介しているので、実践に役立つ内容満載です。
訪問看護師として働き始めたけれど不安がある人、病院勤務との違いに戸惑っている人のほか、これから訪問看護師を目指す人にもおすすめの1冊です。
介護施設看護師の仕事を体験してみませんか?
居宅の訪問型ではなく、施設内の落ち着いた環境で看護の仕事がしたいと考えたことはありませんか?
「カイテク」は、履歴書の提出や面接もなく、スキマ時間で「稼げる」単発バイトアプリです。
高単価の求人も多く、短時間~OK。介護施設の求人も多く、別の職場を体験してみたいな、転職を考えているという方にはぴったりのアプリです。
まずは無料登録してどんな求人があるかチェックしてみませんか?
投稿者プロフィール
- 看護師
- 看護師歴20年。病棟から介護施設・訪問看護などで勤務。2020年からライター活動を開始。みなさまのお役に立てるような記事を作成したいです。どうぞよろしくお願いいたします。
最新の投稿
 訪問看護2023年6月7日【デイサービス看護師の役割】を解説!観察力と真心をもって働く
訪問看護2023年6月7日【デイサービス看護師の役割】を解説!観察力と真心をもって働く 訪問看護2023年4月25日デイサービス看護師が「辛い」と感じるときの原因と解決策は?
訪問看護2023年4月25日デイサービス看護師が「辛い」と感じるときの原因と解決策は? 訪問看護2023年4月14日デイサービス看護師の仕事内容は?どんな人が向いている?
訪問看護2023年4月14日デイサービス看護師の仕事内容は?どんな人が向いている? 訪問看護2023年3月28日【看護師ものんびり働きたい】ねらいたい職場6選!探し方は?
訪問看護2023年3月28日【看護師ものんびり働きたい】ねらいたい職場6選!探し方は?



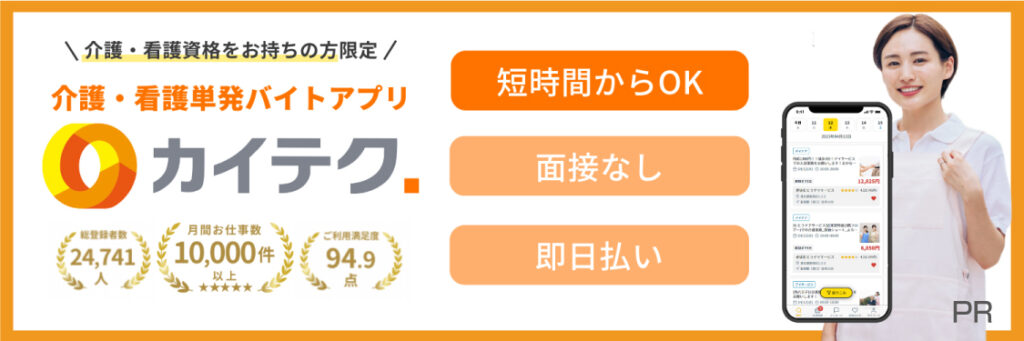
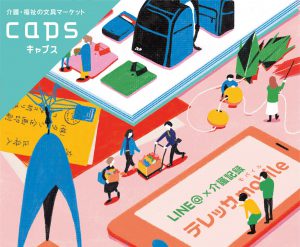
.jpg)
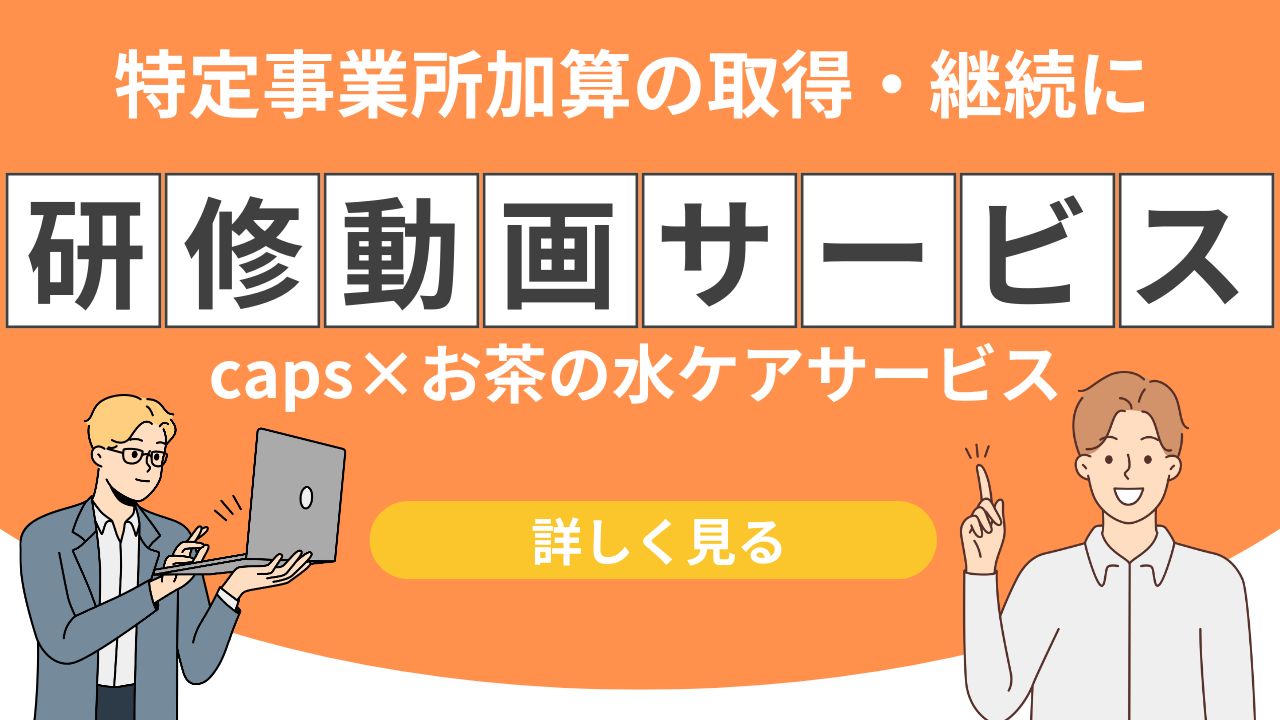

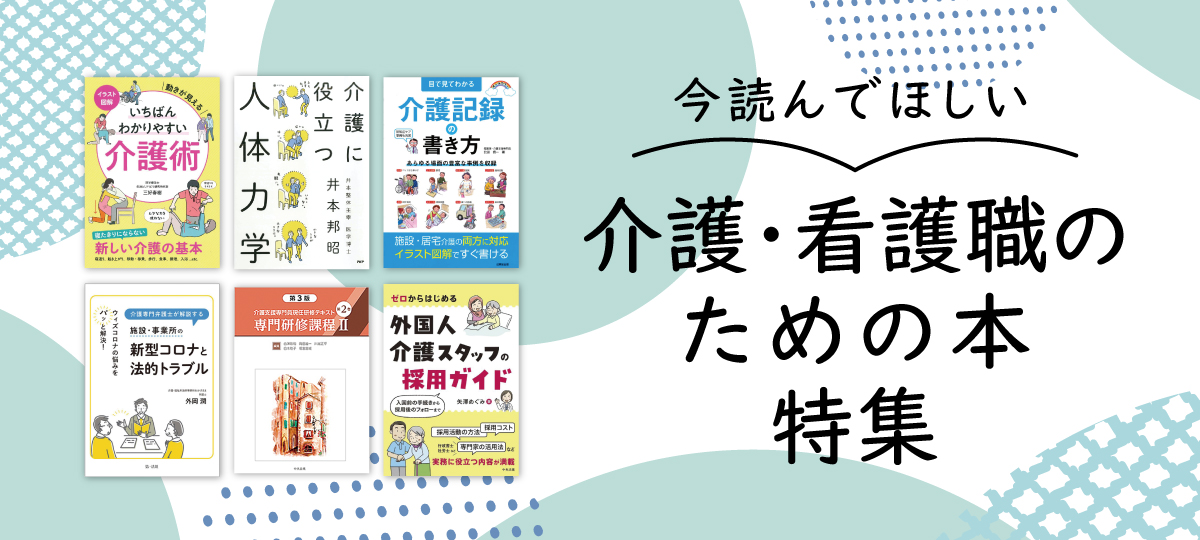
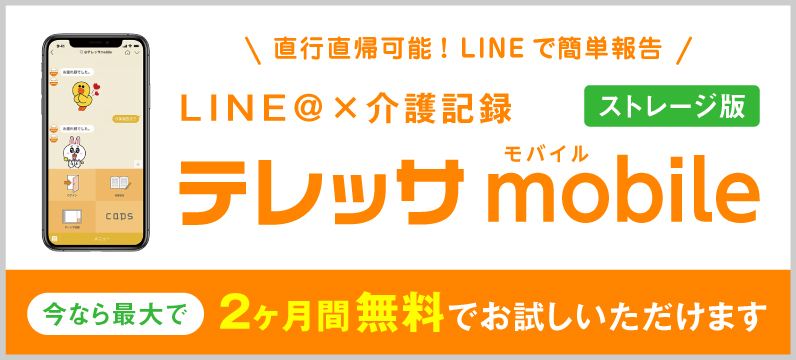

コメント