訪問介護実施記録には利用者の印鑑押印は必要なのでしょうか。
実施記録は、利用者やサービス提供責任者などさまざまな人にチェックされ、利用者に印鑑を押してもらい、責任者もチェックの意味で印鑑を押すのが習慣となっていました。
しかし近年、ICT化、印鑑レスが一般的となり、訪問介護の実施記録に押印についても廃止する事業所や、疑問を感じる事業所も増えてきています。
今回は、訪問介護の実施記録の確認印欄についてと近年の流れ、印鑑の役割や廃止するメリットについて紹介します。
訪問介護のサービス実施記録に利用者の印鑑押印欄がある理由と現状

サービス実施記録とは、いつ、誰が、利用者にどんなサービスを提供したのか、利用者の体調の様子などを記録する書類です。
サービス提供記録や訪問介護記録とも呼ばれ、報酬請求の根拠として使われます。
職員同士で利用者の状態について共有したり、利用者や利用者の家族が、どんなサービスを受けたのかを把握するといった役割もありますよね。
では、そのサービス実施記録に印鑑の押印欄がある理由を見ていきましょう。
サービス実施記録に確認印欄がある理由
紙の実施記録の多くの書式には利用者や責任者に押印してもらう確認印欄がついているのが一般的でした。
この欄はどういった理由からついていたのでしょうか?
全国で初めてサービス実施記録を作成したのは「キャプス」です。
開発当時、いろいろな伝票や契約書にも押印欄はあるし、「サービス実施記録にも押印欄があったほうがいいよね」と考えて押印欄を加えた。というのが理由です。
販売開始後、キャプスの書式は、全国で一般的な介護記録の書式として扱われ、多くの印刷会社やメーカーなどでも類似の記録用紙が販売されてきました。
こうした流れから、ほぼすべての介護事業所が利用者印・責任者の確認印を押すことが当たり前になっていたことと思います。
確認印を押してもらうことのメリットとしては、利用者の手に必ず一度記録が手渡され、実施された内容を確認する流れができる、また、責任者にも実施したサービス内容について確認してもらう流れができるといった部分でしょう。
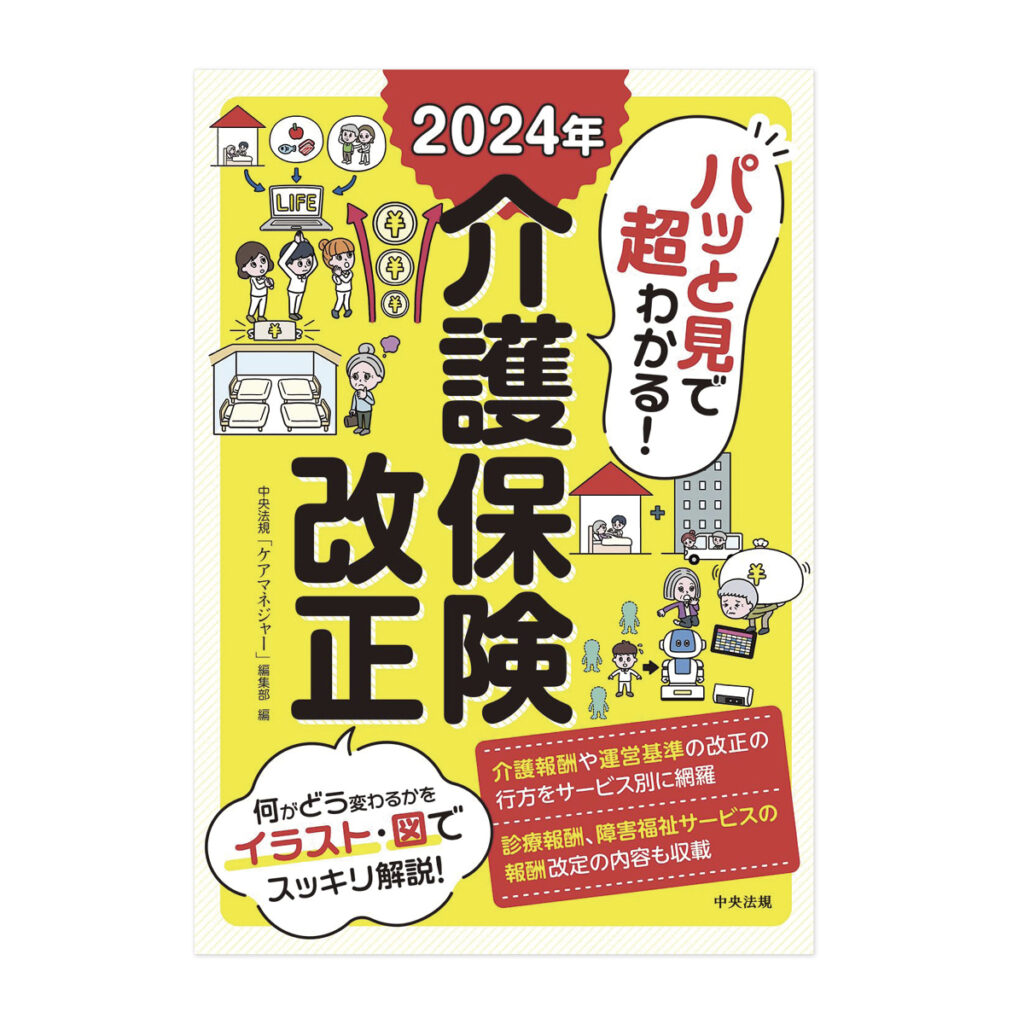
パッと見で超わかる!2024年介護保険改正
2024年に行われる介護保険改正の内容を、サービス別にとことんわかりやすく図解。
Q&Aも交えて改正内容をいち早くまとめられています。
同時に行われる医療・障害に関する報酬改定の内容も網羅し、相談援助職はもちろん、介護サービスにかかわる管理職・現場スタッフ必読の一冊。
サービス実施記録の現状
紙の記録が一般化し、記録➡利用者確認(印)➡責任者確認(印)の流れが確立していましたが、コロナ禍を経て、感染予防や効率化を目的に、急速にICT化が進んできました。
それまで紙の記録が一般的であったのが、国や自治体の補助金・助成金の後押しもあり、システムやアプリに切り替える施設や事業所が急増し、2023年現在、中~大規模事業所はほとんどシステム化が進んでいるといっても過言ではありません(自社調べ)。
しかし一方で、小~中規模の介護事業所では、高齢ヘルパーの問題、費用負担の問題などからシステムに切り替えることができないといった課題を抱えているところも多くあります。
サービス実施記録の印鑑は必ず必要?不要?

既にシステム化が進んでいる事業所が多いため、結論としては出ているのですが、確認印が必要か不要かで言うと、法律上は不要だと言えます。
法律上定められているのは、「利用者に実施したサービスについて確認をとること」であり、「確認印をもらうこと」ではありません。
しかし、これまでの紙の記録の流れから、システム化がスタートしたばかりの頃は押印をなくすことの不安の声が多かったため、多くのシステムで「システムで記録したものをその場で紙出力できる」機能や「利用者に押す動作をしてもらい、デジタル印をつける」機能などがありました。現在も、アプリやシステムによっては、電子チェックという形で、利用者宅でQRコードを読み取るなどの機能がある場合もありますが、そもそも法律的に必要のないものであれば、不要と考える事業所も多いのが実際のところ。
デジタルでの記録が多くなり、徐々にペーパーレス・印鑑レスに抵抗がなくなってきたという流れです。
こうして、システム化、記録のデジタル移行をした事業所にとっては押印が「ないもの」が一般的になってきていますが、紙の記録を利用している事業所は、まだ半数ほどは確認印欄が必要と考えています。(自社調べ)
理由としては、利用者側がこれまでの習慣から押印をしないことに不安を感じる、であったり、自治体によっては監査で指摘される、といった理由があります。
利用者側にはきちんと説明をし、事業所の方針を伝えるということが必要になりますが、監査で指摘されるというのは事業所としては避けたい点ですよね。
何度もこういった問い合わせをキャプスにいただくこともありましたが、結果としては「法律上定められていない」ということと、全国で多くの事業所が既にシステムや確認印欄のない記録用紙を実際に使っているのになぜ?というところで多くの自治体は納得することが多いです。
こうした業界の流れを受け、キャプスも2023年9月より、すべてのサービス実施記録から確認印欄を廃止することとなりました。
印鑑を廃止するメリット

印鑑廃止で得られる最大のメリットは、業務の効率化です。
これまでは押印欄があるために、直帰ができなかったり、月末月初に記録を事業所に持っていく必要があったり、また、印鑑をもらい忘れた場合には利用者の家に改めて訪問したりと、時間を割く必要がありました。
印鑑を廃止することで、こうした移動時間の削減、サービス実施記録の電子化も進みやすくなり、時間や場所にとらわれない働き方ができるようになります。
確認印は不要!テレッサモバイルの導入もおすすめ
確認印は法律上は「不要」ということをお伝えしてきましたが、「それならもう電子化してもいいな」と思われた方もいるのでは?
テレッサモバイルは、サービス実施記録の部分のみを電子化できる、記録に特化したアプリです。
シンプルな機能性、また、多くの人が活用しているLINEを使ったアプリなので、アプリやシステムに苦手な方も、高齢のヘルパーさんでも、スムーズに操作することができます。
確認印が気になって電子化を躊躇していた事業所も多いと思いますが、これを機に、サービス実施記録の電子化を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
訪問介護の実施記録に印鑑が必要と思い込んでいる人が多いですが、実は必要ないということをわかっていただけたと思います。
印鑑をなくせば、業務効率が向上し、スタッフが働きやすくなるだけでなく、利用者にとっても面倒な作業や負担が減るはずです。
印鑑不要であることを事業所内で周知するためにも、まずは確認印欄のない書類を使い、電子化という次のステップにスムーズに移行できるよう工夫すると良いでしょう。
投稿者プロフィール

-
介護・福祉の総合マーケットキャプスの管理者です。
介護事業所・介護に携わる皆様のお役立ち情報を発信しています。
最新の投稿
 訪問介護2023年11月22日冬の感染症を予防する|介護事業所&施設向け種類別感染対策まとめ
訪問介護2023年11月22日冬の感染症を予防する|介護事業所&施設向け種類別感染対策まとめ 居宅介護2023年11月21日ケアマネさんにおすすめの本2023最新版|今年これだけは読みたい7選
居宅介護2023年11月21日ケアマネさんにおすすめの本2023最新版|今年これだけは読みたい7選 介護ニュース2023年10月6日介護施設や介護事業所も|アルコールチェック義務化が延期され2023年12月へ
介護ニュース2023年10月6日介護施設や介護事業所も|アルコールチェック義務化が延期され2023年12月へ キャプスの商品・サービス2023年8月28日2024年度版|キャプスの手帳シリーズ人気ランキング!
キャプスの商品・サービス2023年8月28日2024年度版|キャプスの手帳シリーズ人気ランキング!


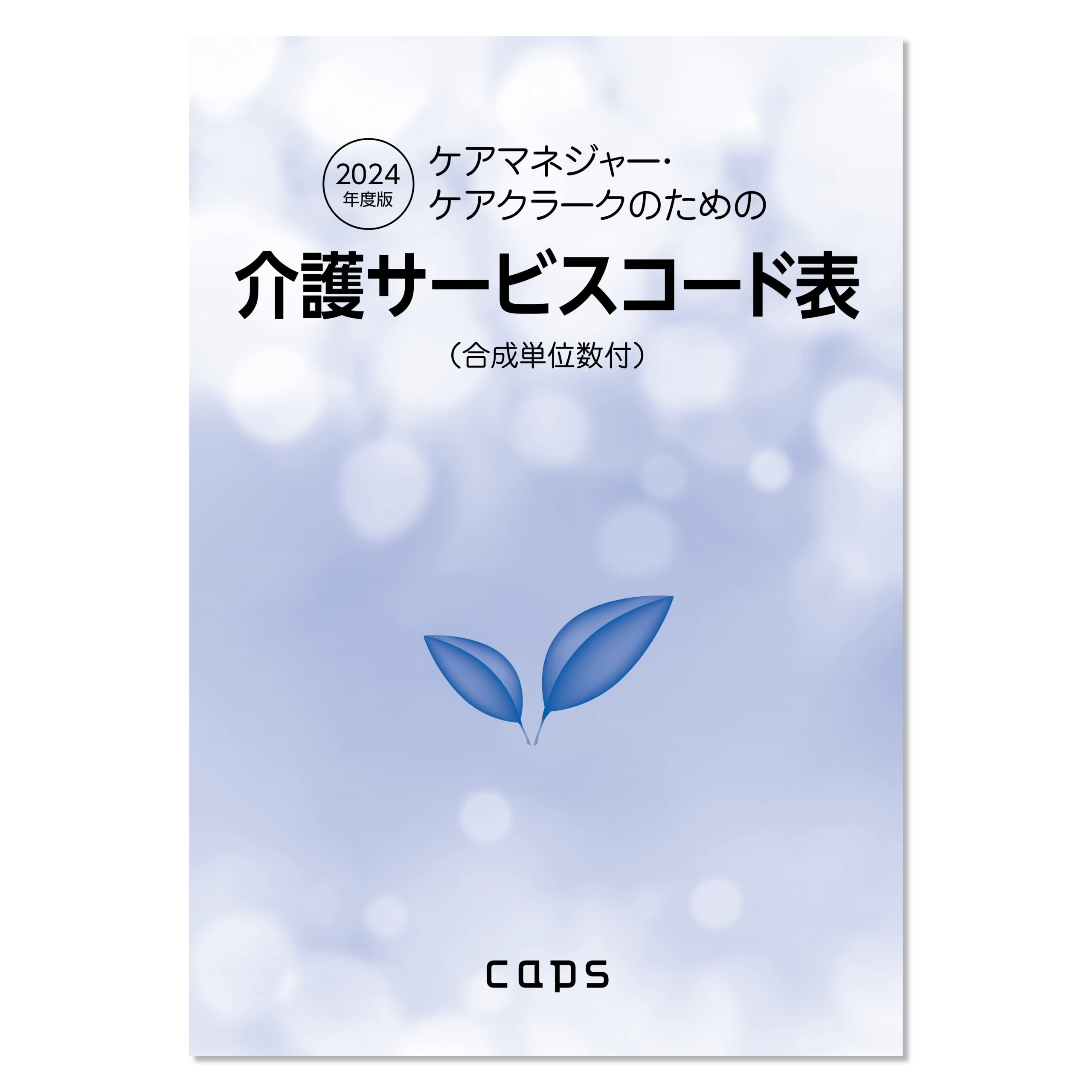
.jpg)
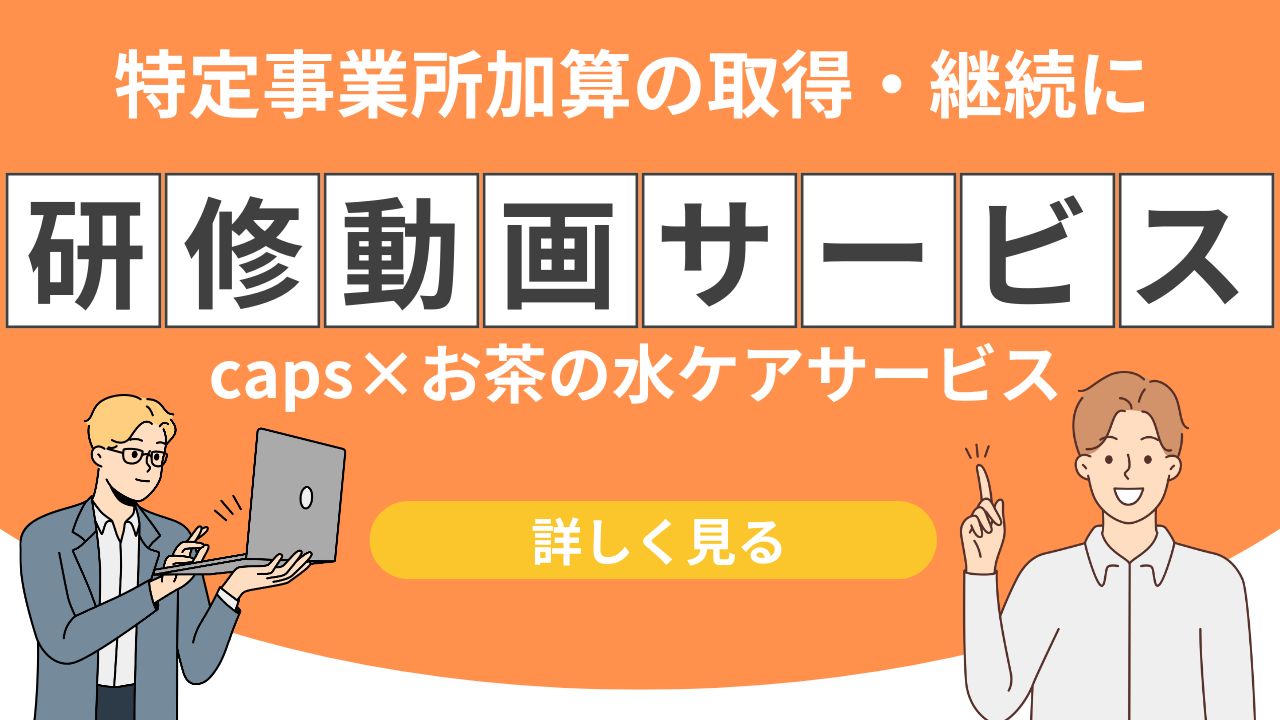

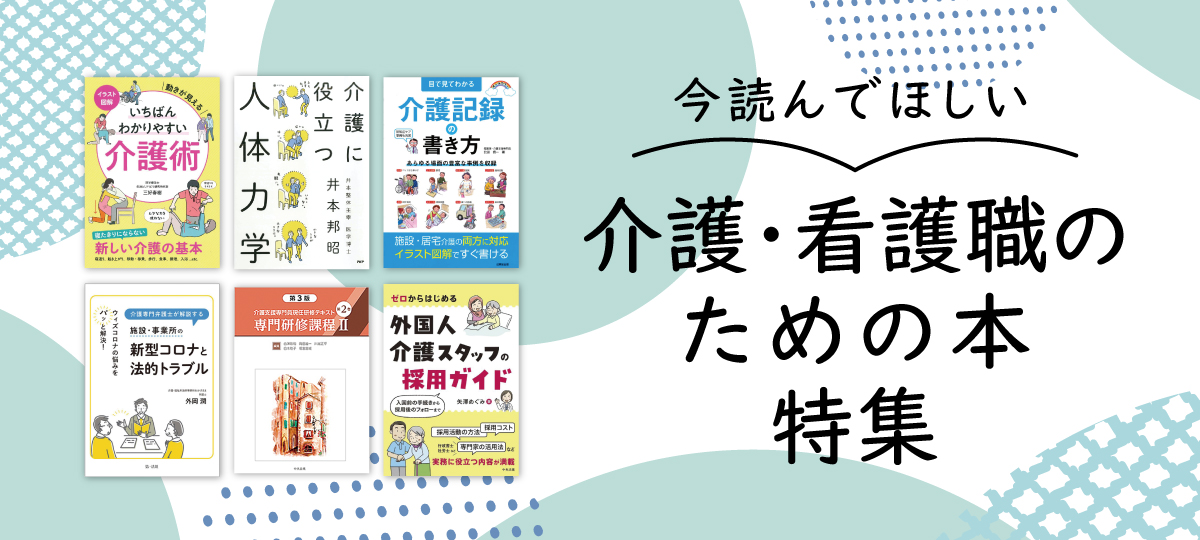
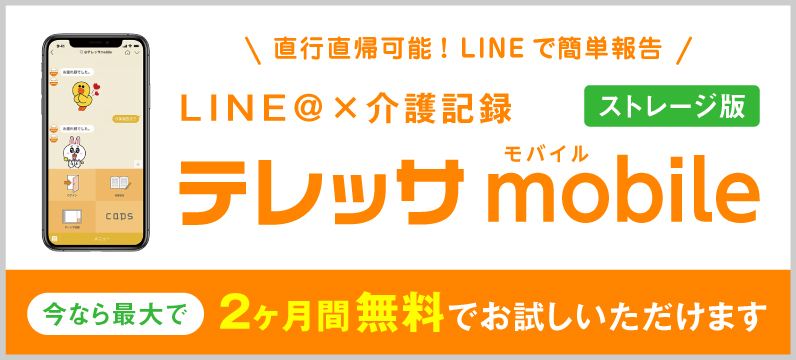

コメント